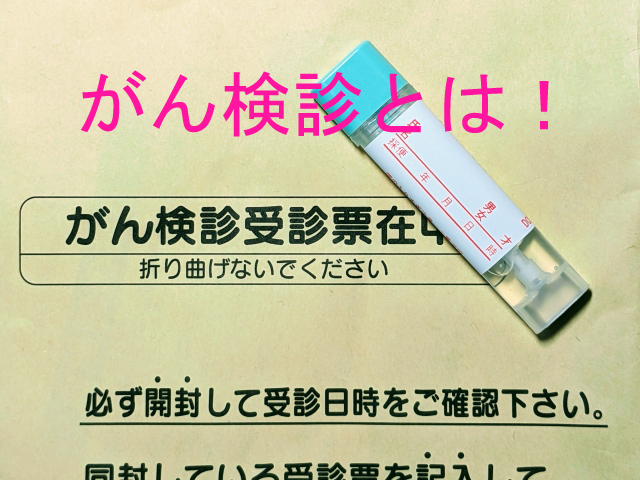
がん検診とは、症状がない健康な人を対象に、がんを早期に発見するための検査です。早期にがんを発見し、適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減らすことが目的とされています。
一般的な健康診断とは異なり、がん検診は特定の部位のがんに焦点を当てた検査が行われます。もし、がんの疑いが見つかった場合には、精密検査(二次検診)を行い、がんの種類や進行度などを詳しく調べ、治療方針を立てるのに役立てます。
国が推奨するがん検診
国(厚生労働省)が科学的根拠に基づき、死亡率減少効果が認められているとして推奨しているがん検診は以下の5種類です。これらの検診は、市区町村や職域などで実施されています。
| がんの種類 | 対象年齢 | 受診間隔 | 主な検査方法 |
|---|---|---|---|
| 胃がん | 50歳以上 | 2年に1回 | 胃部X線検査または胃内視鏡検査(いずれか一方) |
| 大腸がん | 40歳以上 | 1年に1回 | 便潜血検査(免疫法) |
| 肺がん | 40歳以上 | 1年に1回 | 胸部X線検査、喀痰細胞診(喫煙者など) |
| 乳がん | 40歳以上 | 2年に1回 | マンモグラフィ |
| 子宮頸がん | 20歳以上 | 2年に1回 | 細胞診 |
注記
- 上記は一般的な推奨であり、自治体や医療機関によっては対象年齢や検査内容が異なる場合があります。
- 胃がん検診の胃部X線検査は、40歳以上も対象となる場合があります。
- 肺がん検診では、喫煙指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が高い方には喀痰細胞診が追加されます。
- 乳がん検診では、視触診は推奨されていません。
- 子宮頸がん検診では、HPV検査が導入されている自治体もあります。
最新の情報や詳細については、お住まいの市区町村や加入している健康保険組合などにお問い合わせください。
任意型検診とは
任意型検診とは、国が推奨する対策型検診とは異なり、個人の希望に基づいて医療機関などが任意で提供するがん検診です。人間ドックなどに含まれるがん検診がこれにあたります。
任意型検診の特徴
- 対象: 年齢などの制限がなく、希望すれば誰でも受診できます。
- 検査内容: 医療機関によって提供される検査内容が異なり、対策型検診には含まれない検査(腫瘍マーカー検査など)が含まれることもあります。
- 費用: 原則として自己負担となりますが、加入している健康保険組合によっては補助金が出る場合があります。
- 目的: 個人の判断で、より詳細な検査を受けたい、特定の部位のがんリスクを調べたいといった場合に利用されます。
任意型検診は、ご自身の健康状態やリスクに合わせて検査内容を選択できるメリットがありますが、中には科学的根拠が確立されていない検査も含まれている可能性がある点に注意が必要です。受診を検討する際は、検査の目的や内容について医師とよく相談することが大切です。
がん検診で見つかる、さまざまな病気
がん検診では、主にがんの早期発見を目的としていますが、検査の種類によっては、がん以外にもさまざまな病気や異常が見つかることがあります。
以下に、がん検診の種類ごとに、がん以外に見つかる可能性のある主な病気や異常をまとめました。
1. 胃がん検診(胃部X線検査、胃内視鏡検査)
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍: 胃や十二指腸の粘膜が深く傷ついた状態。
- 胃炎: 胃の粘膜の炎症。慢性的なものと急性的なものがあります。
- 胃ポリープ: 胃の粘膜にできた良性の腫瘍。種類によってはがん化のリスクがあるものも。
- 食道裂孔ヘルニア: 胃の一部が食道の方へ脱出する状態。
- 逆流性食道炎: 胃酸が食道に逆流し、炎症を起こす病気。
2. 大腸がん検診(便潜血検査)
- 大腸ポリープ: 大腸の粘膜にできた良性の腫瘍。種類によってはがん化のリスクがあるものも。
- 痔: 肛門周辺の血管や組織が炎症を起こしたり、腫れたりする病気。
- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病など): 大腸の粘膜に炎症が起こる病気。
- 大腸憩室症: 大腸の壁の一部が外側に袋状に飛び出した状態。
3. 肺がん検診(胸部X線検査、喀痰細胞診)
- 肺炎: 肺の炎症。細菌やウイルスなどが原因で起こります。
- 肺結核: 結核菌による感染症。
- 肺気腫・慢性閉塞性肺疾患(COPD): 肺の組織が破壊され、呼吸が困難になる病気。
- 気管支拡張症: 気管支が異常に広がり、痰がたまりやすくなる病気。
- 胸水: 肺と胸壁の間に液体が異常にたまった状態。
- 心臓肥大: 心臓が大きくなった状態。胸部X線検査で発見されることがあります。
4. 乳がん検診(マンモグラフィ)
- 乳腺症: 乳房の痛みやしこり、分泌などを引き起こす良性の変化。
- 線維腺腫: 乳房にできる良性の腫瘍。
- 乳腺嚢胞: 乳房の中に液体がたまった袋状のもの。
- 石灰化: 乳腺組織にカルシウムが沈着したもの。良性のことが多いですが、がんの可能性も否定できません。
5. 子宮頸がん検診(細胞診)
- 異形成: 子宮頸部の細胞に異常が見られる状態。軽度、中等度、高度があり、高度異形成はがんの前段階と考えられています。
- 良性ポリープ: 子宮頸部や子宮内膜にできる良性の腫瘍。
- 炎症: 細菌やウイルス感染などによる子宮頸部の炎症。
任意型検診で見つかる可能性のある病気・異常
任意型検診では、さまざまな部位の画像検査(CT、MRI、超音波など)や血液検査(腫瘍マーカーなど)が行われることがあります。これにより、以下のような病気や異常が見つかる可能性もあります。
- 肝臓疾患: 脂肪肝、肝炎、肝硬変、肝血管腫など
- 胆嚢疾患: 胆石、胆嚢ポリープなど
- 膵臓疾患: 膵炎、膵嚢胞など
- 腎臓疾患: 腎結石、腎嚢胞など
- 前立腺肥大症: 前立腺が肥大し、排尿困難などを引き起こす病気(男性の場合)
- 卵巣嚢腫: 卵巣に液体がたまった袋状のもの(女性の場合)
- 甲状腺疾患: 甲状腺腫、甲状腺機能異常など
- 動脈硬化: 血管が硬くなる状態(頸動脈エコーなどで評価)
- 生活習慣病: 糖尿病、高血圧、脂質異常症など(血液検査で評価)
重要な注意点
- がん検診で見つかる異常のすべてががんであるとは限りません。多くは良性の病気や変化です。
- 異常が見つかった場合は、必ず精密検査(二次検診)を受け、医師の診断を仰ぐことが重要です。
- 腫瘍マーカー検査は、がんの早期発見には有用でない場合があり、単独でのスクリーニングには推奨されていません。異常値が出た場合でも、必ずしもがんであるとは限りません。
がん検診は、がんの早期発見だけでなく、他の病気や異常に気づくきっかけにもなることがあります。定期的な受診を心がけ、ご自身の健康状態を把握しましょう(*^^)v


