「うちの親はまだ元気だから大丈夫」 そう思っていても、ある日突然、親が認知症と診断されることは決して他人事ではありません。動揺や今後の介護への不安とともに、実は深刻な問題が一気に浮上します。それが「相続対策」です。
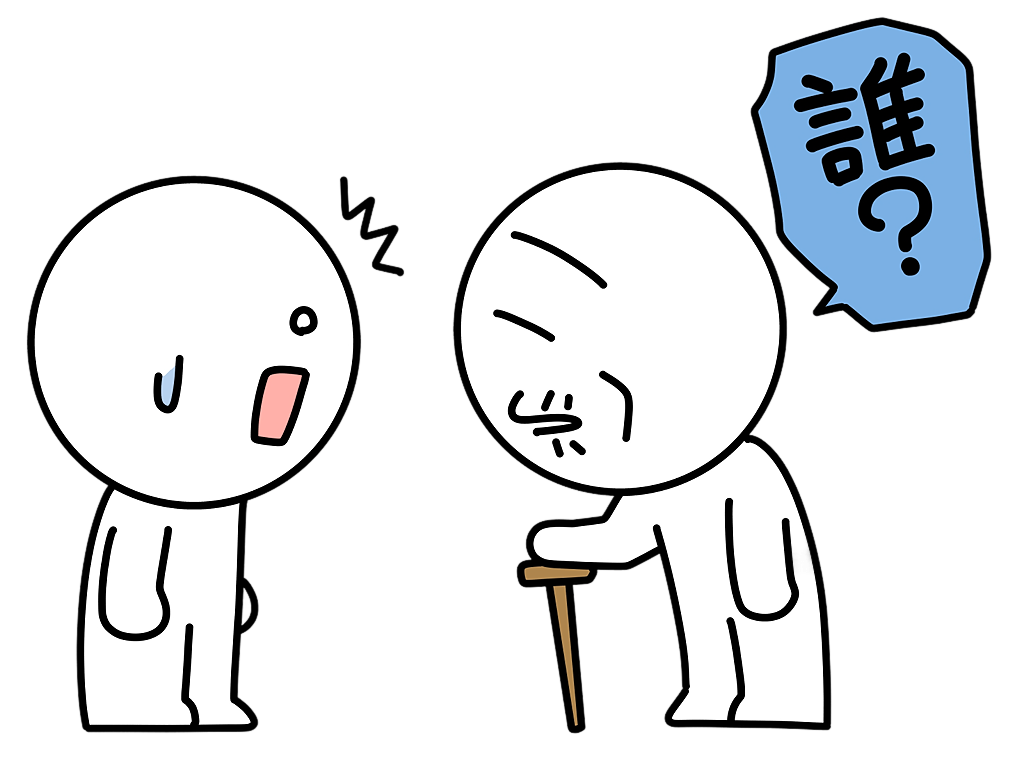
結論から言うと、親が認知症と診断され、意思能力がないと判断された後では、有効な相続対策はほとんどできなくなります。
この記事では、なぜ認知症になると相続対策が難しくなるのか、そして手遅れになる前に何をすべきかを詳しく解説します。
なぜ認知症になると相続対策ができないのか?
相続対策には、遺言書の作成、生前贈与、不動産の売却や組み換えなど、様々な法律行為が伴います。法律行為が有効に成立するためには、その行為を行う本人に「意思能力」があることが大前提です。
意思能力とは、自分が行う行為の結果を正しく理解し、判断できる能力のことを指します。認知症が進行すると、この意思能力が失われた状態と判断される可能性が高まります。
| 意思能力がある状態 | 意思能力がない状態(認知症など) |
| ・契約内容を理解できる ・自分の財産を誰にどう遺したいか判断できる | ・契約内容を理解できない ・自分の行為がどんな結果を招くか判断できない |
| → 法律行為は有効 | → 法律行為は無効 |
意思能力がない状態で行われた契約や遺言は、後から「無効」であると主張されるリスクが非常に高く、法的に効力を持ちません。つまり、親が認知症になってからでは、相続税対策のための生前贈与も、実家を売却して介護費用に充てることも、円満な相続のための遺言書作成も、すべてできなくなってしまうのです。
口座凍結という現実的なリスク
さらに深刻なのが、預金口座の凍結です。
金融機関は、口座名義人が認知症になったことを知ると、本人の財産を守るという観点から、預金口座の取引を停止(凍結)する措置を取ります。これは、詐欺被害や、一部の家族による無断の引き出しを防ぐための正当な対応です。
一度口座が凍結されると、たとえ家族であっても、キャッシュカードでの引き出しはもちろん、窓口での手続きも原則としてできなくなります。親の介護費用や医療費、施設への入居金などを親の預金から支払おうとしても、それができなくなってしまうのです。
「認知症と診断されたら即凍結」というわけではありませんが、例えば、家族が窓口で「親が認知症で来られないので代わりに…」といった趣旨の発言をしたり、本人が窓口で何度も同じことを聞くなど、言動に明らかな変化が見られたりした場合に、金融機関が認知症の事実を把握する可能性があります。
どこからが「意思能力なし」?認知症の判断基準
では、どの段階から「意思能力がない」と判断されるのでしょうか。法的に明確な線引きがあるわけではありませんが、一つの重要な指標となるのが医師による診断です。
診断の過程で、認知機能の低下を客観的に評価するために、様々な検査が行われます。その代表的なものが「長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」です。これは、記憶力を中心とした9つの質問で構成され、認知症の疑いを判断するスクリーニング検査として広く用いられています。
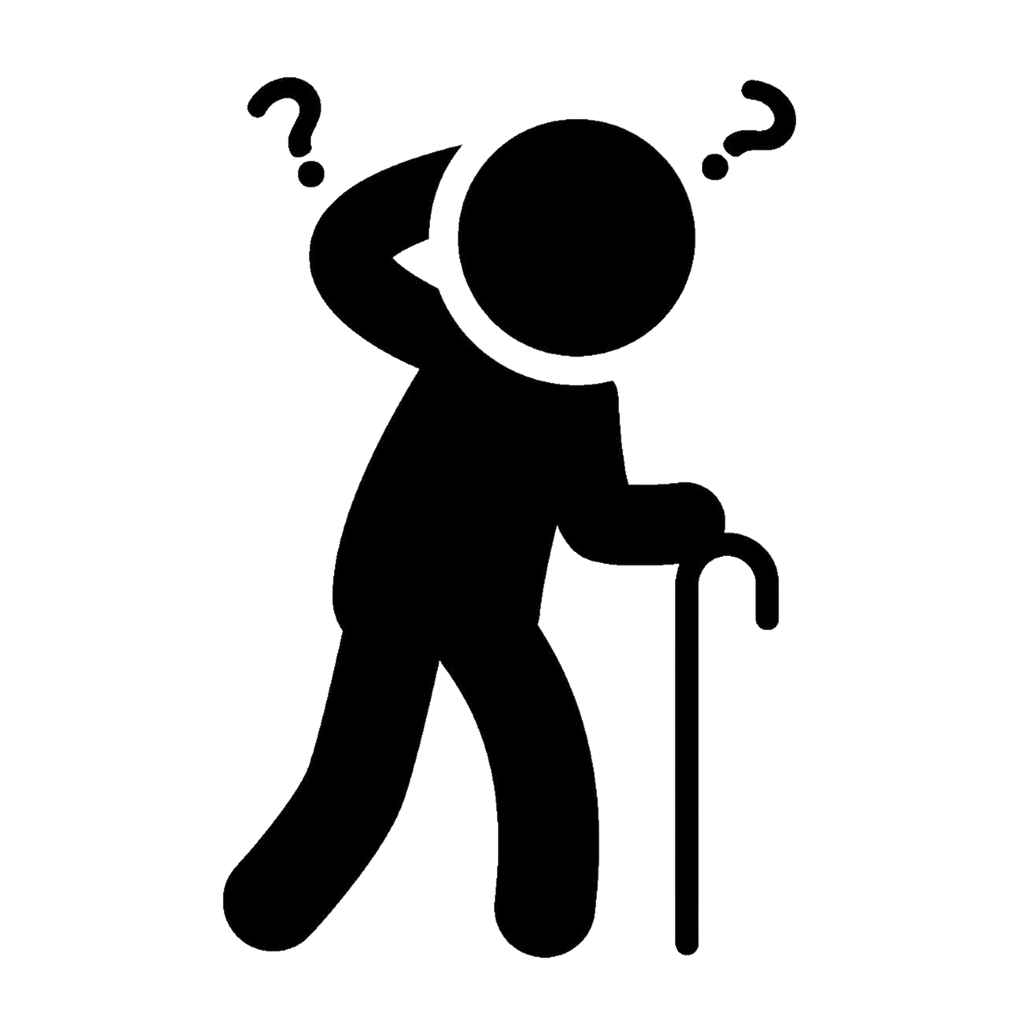
長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
| 質問項目 | 内容 | 配点 |
| 1. 年齢 | 「お歳はいくつですか?」と問う。(2歳の誤差までは正解) | 1点 |
| 2. 日付の見当識 | 「今日は何年何月何日ですか?何曜日ですか?」と問う。 | 各1点 計4点 |
| 3. 場所の見当識 | 「私たちが今いるところはどこですか?」と問う。 | 2点 |
| 4. 言葉の記銘 | 異なる3つの単語(例:桜、猫、電車)を覚えてもらう。 | 各1点 計3点 |
| 5. 計算 | 「100から7を順番に引いてください」と指示する。(100-7=93, 93-7=86) | 各1点 計2点 |
| 6. 数字の逆唱 | 「私が言う数字を逆から言ってください」と指示する。(例:6-8-2, 3-5-2-9) | 各1点 計2点 |
| 7. 言葉の遅延再生 | 質問4で覚えてもらった3つの単語を再度言ってもらう。 | 各2点 計6点 |
| 8. 物品の再生 | 5つの品物(例:時計、鍵、ペンなど)を見せた後、隠して何かあったかを答えてもらう。 | 各1点 計5点 |
| 9. 言葉の流暢性 | 「知っている野菜の名前をできるだけ多く言ってください」と促す。(10秒で打ち切り) | 6個以上で1点~ (10個以上で5点) |
| 合計 | 30点満点 |
【評価の目安】
- 20点以下:認知症の疑いあり
- 21点以上:非認知症の可能性
ただし、この点数だけで認知症や意思能力の有無が断定されるわけではありません。最終的には、医師の総合的な診断や、日々の言動、そして法律行為の際には公証人や司法書士などの専門家が面談を通じて本人の意思能力を確認します。

手遅れになる前に!3つの有効な対策
親が元気で、判断能力がしっかりしているうちしか、有効な対策は打てません。ここでは代表的な3つの方法をご紹介します。
対策1:家族信託(民事信託)
近年、最も柔軟で効果的な対策として注目されているのが「家族信託」です。これは、親(委託者)が元気なうちに、信頼できる子供(受託者)との間で信託契約を結び、財産の管理や処分を任せる制度です。
- メリット
- 親が認知症になっても、受託者である子供が契約内容に基づき、口座凍結の心配なく財産の管理(預金の引き出し、不動産の売却など)を継続できる。
- 成年後見制度と違い、家庭裁判所の監督を受けないため、より柔軟で迅速な財産管理が可能。
- 親の希望に沿った財産の承継先(二次相続以降)まで指定できる。
- デメリット
- 契約書の作成など、専門家(司法書士や弁護士)への依頼費用がかかる。
- 身上監護(介護契約や施設入所契約など)は含まれないため、必要であれば後述の任意後見制度との併用も検討する。
対策2:任意後見制度
元気なうちに、将来自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ支援してもらう人(任意後見人)と、その内容を公正証書による契約で決めておく制度です。
- メリット
- 自分で信頼できる人を後見人に選べる。
- 財産管理だけでなく、介護や生活に関する手続き(身上監護)も任せることができる。
- デメリット
- 実際に判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してから効力が発生するため、すぐに財産を動かせない場合がある。
- 任意後見監督人への報酬が継続的に発生し、家庭裁判所への報告義務など手続きが煩雑になる。
対策3:遺言書の作成
相続発生後のトラブルを防ぐための基本的な対策です。必ず、判断能力が明確なうちに作成しておく必要があります。
- メリット
- 自分の意思で財産の分配方法を決めることができるため、相続人間の争いを防ぐ効果がある。
- デメリット
- あくまで死後の財産承継を決めるものであり、生前の認知症による口座凍結や財産管理の問題は解決できない。
- 法的に有効なものを作成するためには、自筆証書遺言よりも、公証人が作成に関与する公正証書遺言が確実でおすすめ。
【注意】成年後見制度のデメリット
「認知症になったら、成年後見制度を使えばいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」は、あくまで本人の財産を守ることが最優先の制度であり、家族が望むような柔軟な対応ができないケースが多く、多くのデメリットを伴います。
- 積極的な資産活用はできない:本人の財産を減らす可能性のある行為(相続税対策のための生前贈与、収益性の低い不動産の売却など)は、原則として認められません。
- 家族が後見人になれるとは限らない:財産額が大きい場合など、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任されるケースが多く、その場合、本人が亡くなるまで継続的に報酬を支払い続ける必要があります。
- 手続きが煩雑:後見人は家庭裁判所に定期的に財産状況を報告する義務があり、家族にとって大きな負担となります。
- 一度選任されると止められない:原則として、本人が亡くなるまで後見は続きます。
こうした理由から、法定後見制度は「最後の手段」と考え、できる限り事前に「家族信託」や「任意後見」といった対策を講じておくことが賢明です。

まとめ:大切なのは、元気なうちの家族会議
親が認知症と診断されてからでは、打てる手はほとんど残されていません。「親が認知症になったら…」という話は、家族にとって切り出しにくい話題かもしれません。
しかし、見て見ぬふりをして問題を先送りすれば、いざという時に「口座が凍結されて介護費用が引き出せない」「実家を売却できず施設に入れない」といった、より深刻な事態を招きかねません。
最も大切なのは、親が心身ともに元気なうちに、家族全員で将来のことを話し合うことです。この記事をきっかけに、まずはご家族でオープンに話し合う機会を持ってみてはいかがでしょうか。そして、具体的な対策を検討する際には、株式会社CRANEに、ご相談ください。
「家族信託」や「任意後見」についても、今後詳しく説明していきますね(*^^*)v


