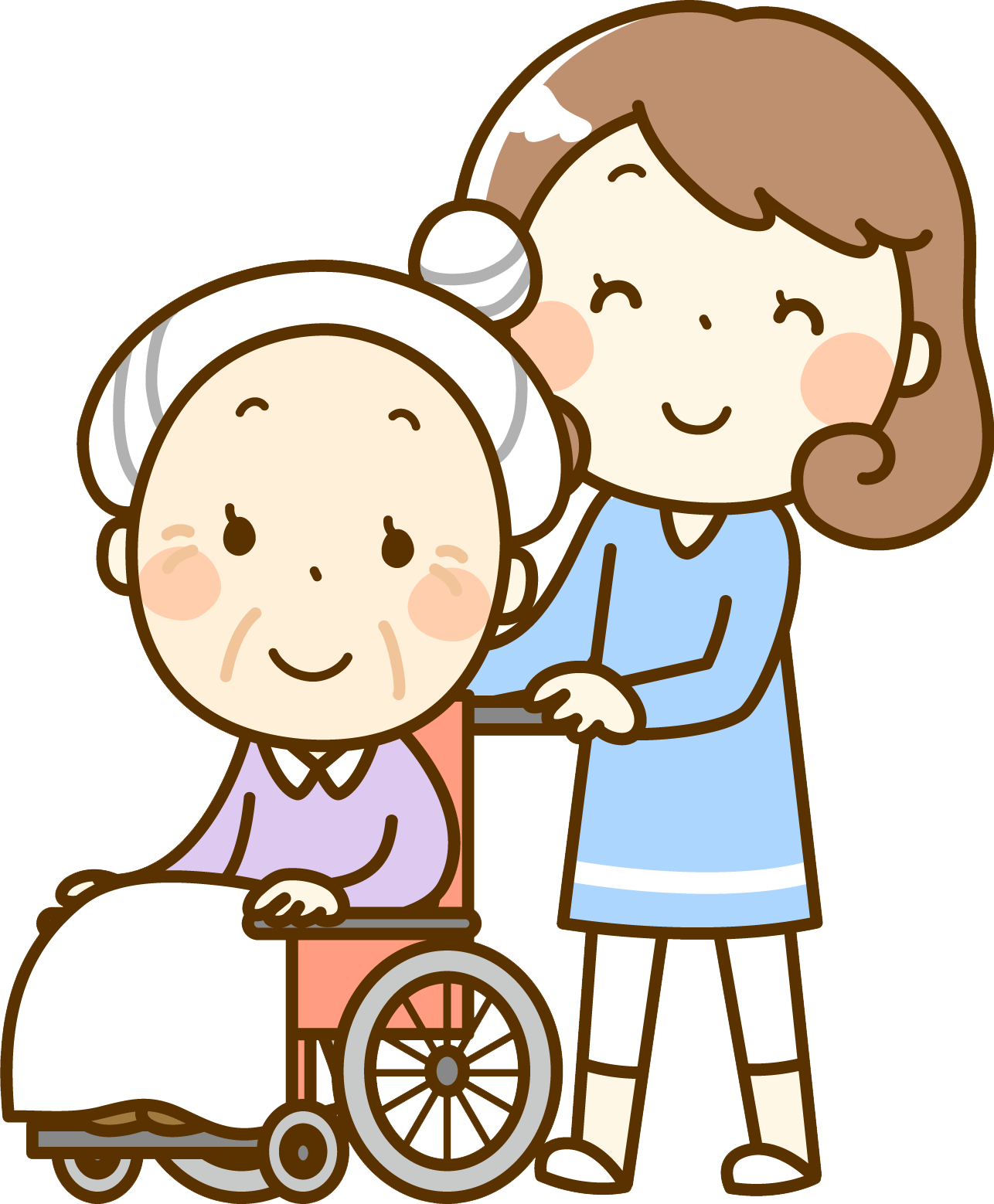
【会話で解説】親の介護の苦労は報われないの?
【登場人物】
- 長男 かつお: 10年以上、母親の介護を一身に担ってきた。真面目で責任感が強い。
- 次男 たらお: 遠方に住み、介護にはほとんど関わってこなかった。現実的な性格。
- FP 千鶴: 親族の相続問題に詳しいファイナンシャルプランナー。穏やかで的確なアドバイスをする。
プロローグ:兄弟の不協和音
FP千鶴の事務所
かつお: 「納得いかない!俺は10年間、仕事をセーブして母さんの介護をしてきたんだ。それなのに、ほとんど顔も見せなかったお前と、母さんの遺産の取り分が同じなんて、おかしいだろ!」
たらお: 「兄さんが大変だったのはわかるよ。でも、法律で決まってるんだから仕方ないじゃないか。兄弟なんだから、相続分は半分ずつ。シンプルだろ?」
かつお: 「その『シンプル』の一言で片づけるな!こっちの苦労も知らないで…!」
千鶴: 「まあまあ、お二人とも落ち着いてください。かつおさんのそのお気持ち、とてもよく分かります。今日は、なぜそのような状況が起きてしまうのか、そして、本来どうすべきだったのかを一緒に考えていきましょう。」
なぜ報われない?「法定相続」という絶対的なルール
千鶴: 「たらおさんがおっしゃる通り、お母様が遺言書を遺していなかった場合、法律で定められた『法定相続分』に従って財産を分けるのが大原則になります。お子様はかつおさんとたらおさんのお二人なので、法定相続分はちょうど2分の1ずつ。これは、どちらかが介護をしたかどうかとは、全く関係なく決まるルールなんです。」
かつお: 「それが法律の限界ってやつか…。でも、俺の頑張りは本当にゼロ評価なのか?『寄与分』っていう制度があるって聞いたことがあるぞ!」
希望の光?それとも…「寄与分」の厳しい現実
千鶴: 「はい、寄与分(きよぶん)という制度ですね。亡くなった方の財産の維持や増加に『特別な貢献』をした相続人が、その貢献分を上乗せして相続できる、というものです。」
かつお: 「それだ!俺の介護は、まさに『特別な貢献』だろう!施設に入っていたら、もっとお金がかかったはずなんだから!」
千鶴: 「おっしゃる通りです。しかし、この寄与分が裁判所などで認められるハードルは、実は非常に高のが現実なんです。」
たらお: 「え、そうなの?」
千鶴: 「はい。なぜなら、裁判所は『親族なのだから、ある程度の助け合いや扶養は当たり前』と考える傾向があるからです。寄与分として認められるのは、その“当たり前”のレベルをはるかに超える貢献、と判断された場合だけなんです。」
【寄与分が認められやすいケースとは?】
- 介護のために仕事を辞めた、あるいは収入が大幅に減った。
- 長期間にわたり、ほぼ付きっきりで介護をしていた。
- 本来かかるはずだった高額な施設費用や入院費を、自分の財産から立て替えて支払っていた(その証拠がある)。
- 介護の対価として、親から一切お金を受け取っていなかった。
千鶴: 「これらのことを、介護をしたかつおさんご自身が、日記や領収書といった客観的な証拠で証明しなければなりません。『大変だった』という感情だけでは、なかなか認められないのが実情です。」
もし寄与分が認められたら、相続分はどう変わる?
かつお: 「うーん、ハードルが高いのは分かった…。でも、もし認められたらどうなるんだ?」
千鶴: 「良い質問ですね。では、シミュレーションしてみましょう。お母様の遺産が2,000万円で、仮にかつおさんの寄与分が300万円と認められたとします。」
- まず、遺産全体から寄与分を引きます。 2,000万円−300万円=1,700万円
- この1,700万円を、本来の法定相続分(1/2ずつ)で分けます。 1,700万円÷2人=850万円
- 最後に、かつおさんはこの850万円に、ご自身の寄与分を足します。
- かつおさんの相続分: 850万円+300万円=1,150万円
- たらおさんの相続分: 850万円
たらお: 「なるほど…。兄さんの頑張りが認められれば、確かに差はつくんだな。」
「時すでに遅し」になる前に!介護者がすべきだった3つの対策
千鶴: 「ですが、相続が起きてから寄与分を主張するのは、時間も労力もかかりますし、兄弟間の争いにもなりかねません。一番良いのは、お母様がお元気で、ご自身の意思をはっきり示せるうちに、対策を打っておくことでした。」
かつお: 「対策…?」
千鶴: 「はい。主に3つあります。」
対策1:遺言書
千鶴: 「最も強力なのが遺言書です。『長男のかつおに、財産の〇割(あるいは全財産)を相続させる』とお母様に書いてもらえていれば、原則としてその通りになります。たらおさんには最低限の権利である『遺留分』がありますが、それでも、かつおさんの取り分を大きく確保できます。」
対策2:生前贈与
千鶴: 「お母様が生きているうちに、介護の感謝のしるしとして、かつおさんに財産を贈与してもらう生前贈与も一つの手です。ただし、亡くなる直前の贈与などは相続財産に含めて計算される場合があるので、計画的に行う必要があります。」
対策3:「負担付死因贈与契約」
千鶴: 「そして、今回のケースに特に有効だったかもしれないのが、『負担付死因贈与契約(ふたんつきしいんぞうよけいやく)』です。」
かつお・たらお: 「ふたんつき…?」
千鶴: 「はい。『私が亡くなるまで、身の回りの世話をしてくれるなら、私が死んだらこの家をあなたにあげます』といったように、**介護などの“負担”を条件に、財産を“贈与”することを約束する『契約』**です。遺言と違い、お母様とかつおさんの双方の合意で結ぶものなので、『介護をしてもらう』という親の意思と、『介護をする』という子の意思を、より明確に形に残せるのです。」
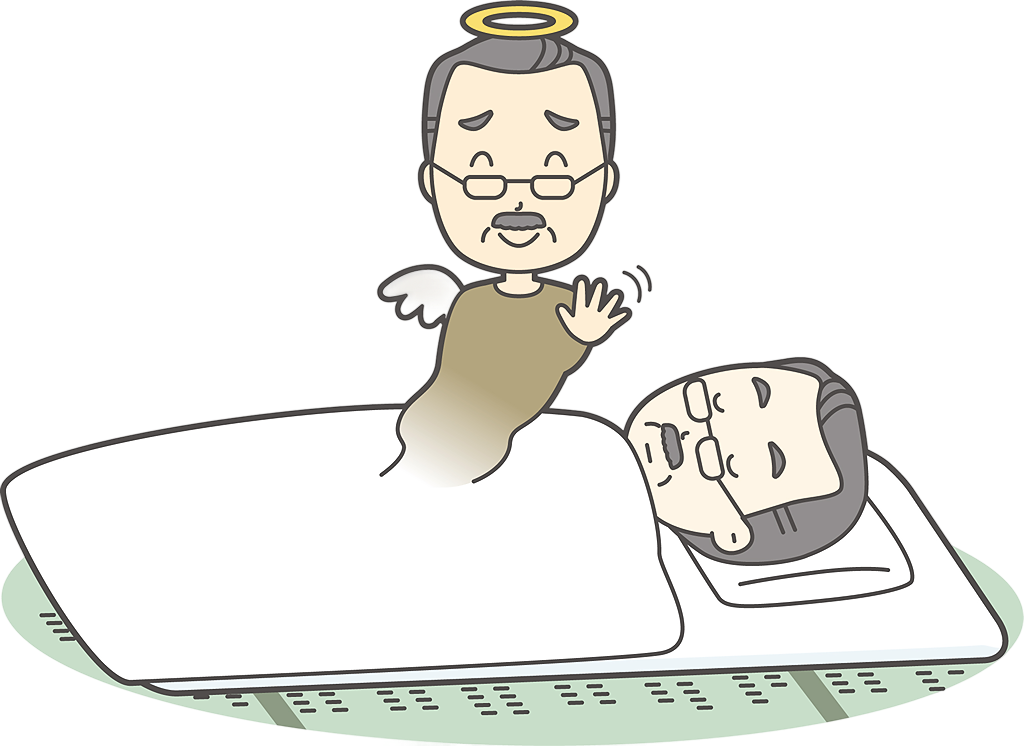
これからのために
かつお: 「こんな契約書があったのか…。もっと早く、母さんが元気なうちに千鶴さんのような専門家に相談に来ればよかったな…。」
たらお: 「兄さん…、今まで本当に苦労をかけたな。ごめん。俺も法律のことばかり言って、兄さんの気持ちを考えていなかった。これからどうすればいいか、ちゃんと一緒に考えるよ。」
千鶴: 「たらおさんがそう言ってくださるなら、まだ遅くありません。寄与分の主張が難しいとしても、兄弟でしっかり話し合って、お互いが納得できる形で遺産分割協議をまとめることは可能です。大切なのは、家族がこれからも良い関係でいられることですから。そのためのサポートは、いつでもさせていただきますよ。」

【ひな形】負担付死因贈与契約書の見本
以下は、あくまでシンプルな見本です。実際に作成する際は、ご自身の状況に合わせて、必ず弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。
負担付死因贈与契約書
贈与者(以下「甲」という)〇〇 〇〇(生年月日)と、受贈者(以下「乙」という)〇〇 〇〇(生年月日)は、本日、以下の通り負担付死因贈与契約を締結する。
第1条(死因贈与)
甲は、甲の死亡をもって、甲が所有する下記不動産を乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
【不動産の表示】
所 在:〇〇市〇〇町〇丁目
地 番:〇〇番〇
地 目:宅地
地 積:〇〇.〇〇平方メートル
第2条(負担)
乙は、本契約の負担として、本契約締結の日から甲が死亡するまでの間、以下の義務を履行する。
(1) 甲と同居し、甲の身の回りの監護および療養看護に努める。
(2) 甲の入院、通院の際には、その手続き、送迎、付き添い等を行う。
(3) 甲の財産管理および公租公課の支払い手続きを補助する。
第3条(契約の履行)
甲の死亡後、乙は速やかに本物件の所有権移転登記手続きを行うものとする。
第4条(契約の解除)
乙が第2条に定める負担を履行しない場合、甲は本契約を解除することができる。
第5条(その他)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、誠実にこれを解決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本書面を2通作成し、甲乙それぞれが署名押印の上、各1通を保有する。
〇〇年〇月〇日
贈与者(甲)
住 所:
氏 名:〇〇 〇〇 ㊞
受贈者(乙)
住 所:
氏 名:〇〇 〇〇 ㊞
まとめ:後悔しないために、今すぐ行動を
介護は、お金には代えられない尊い行為です。しかし、その労力や想いが、相続の場で踏みにじられてしまうのは、あまりにも悲しい現実です。
法律の原則は変えられませんが、生前の準備によって、あなたの苦労が正当に報われる未来を作ることは可能です。
「まだ親は元気だから大丈夫」と思わずに、親子で、そして兄弟姉妹で、相続について話し合うきっかけにしてみてください。そして、少しでも不安があれば、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に相談することをお勧めします。あなたの長年の苦労が、正しく評価されることを心から願っています。


