負担付死因贈与契約とは、贈与者が亡くなったときに財産を無償で譲り渡す「死因贈与契約」に、「受贈者(財産を受け取る人)が一定の義務(負担)を履行すること」を条件として加えた契約のことです。
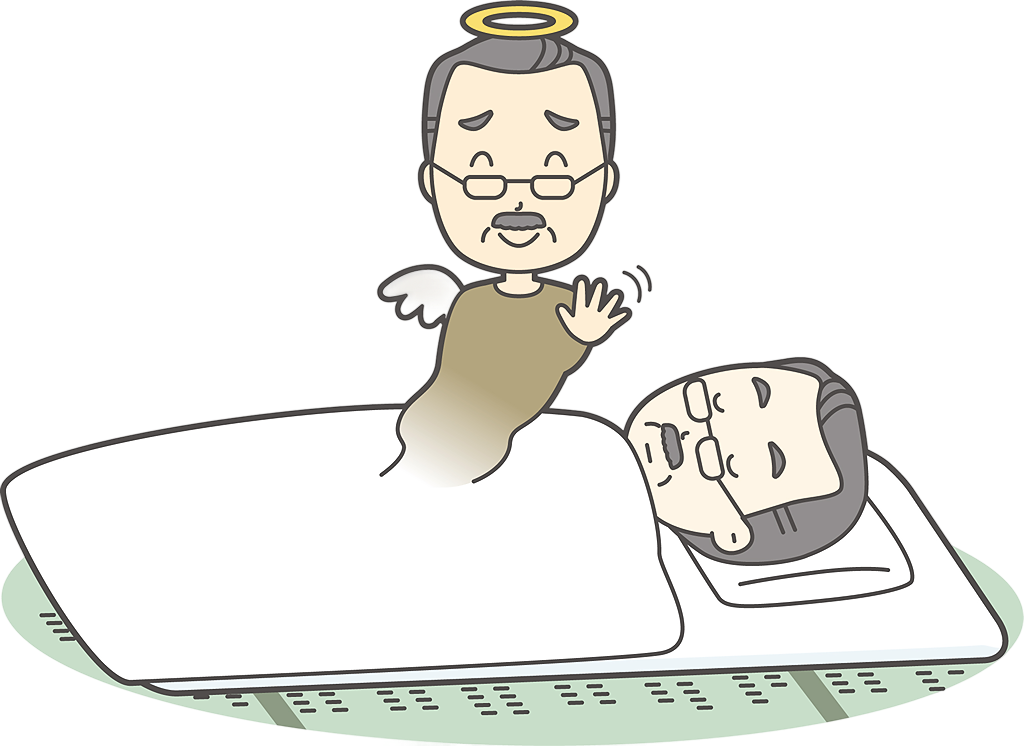
例えば、「私が亡くなったら自宅をあなたにあげる代わりに、私が生きている間は身の回りの世話をしてください」といった内容の契約がこれにあたります。
遺言に代わる財産承継の方法として利用されることがありますが、メリット・デメリットや遺贈との違いを正しく理解した上で活用することが重要です。
負担付死因贈与契約の仕組みと具体例
この契約は、贈与者と受贈者の双方の合意によって成立する「契約」です。贈与者が一方的に行う「遺言」とは異なり、財産を受け取る側の承諾が不可欠です。
【具体的な負担の例】
- 療養看護や生活の面倒を見ること: 高齢の贈与者の身の回りの世話や介護をすること。
- 金銭的な給付: 毎月一定額の生活費を贈与者に渡すこと。
- 特定の債務の弁済: 贈与者が抱える借金を代わりに返済すること。
- ペットの世話: 贈与者が亡くなった後、残されたペットの面倒を見ること。
- 同居: 一人暮らしの贈与者と亡くなるまで同居すること。

メリットとデメリット
負担付死因贈与契約には、贈与者と受贈者の双方にとって以下のようなメリットとデメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
| 贈与者 | ・生前の希望を確実に実現できる (例:介護や生活支援を受けられる) ・受贈者の合意があるため安心感がある | ・一度契約すると原則として一方的に撤回できない (特に受贈者が負担を履行し始めた場合) |
| 受贈者 | ・将来的に財産を取得できる権利が法的に保護される (遺言のように一方的に破棄されるリスクが低い) ・不動産の場合、仮登記をすることで権利を保全できる | ・契約で定められた負担を履行する義務を負う ・贈与者の死後、他の相続人とトラブルになる可能性がある |
負担付死因贈与契約と遺贈の主な違い
「亡くなった後に財産を渡す」という点では遺言による「遺贈」と似ていますが、法的な性質や手続きにおいて重要な違いがあります。
| 負担付死因贈与契約 | 遺贈 | |
| 法的性質 | 契約(贈与者と受贈者の双方の合意が必要) | 単独行為(遺言者が一方的に行う) |
| 合意の要否 | 必要 | 不要 |
| 撤回の自由度 | 原則として一方的な撤回は困難 (特に負担履行後) | 原則としていつでも自由に撤回・変更が可能 |
| 書面の要否 | 口頭でも成立するが、公正証書が強く推奨される | 法律で定められた形式の遺言書が必須 |
| 年齢要件 | 贈与者は原則18歳以上 | 遺言者は15歳以上 |
| 不動産の税金 | 不動産取得税:課税 登録免許税:税率 2.0% | 不動産取得税:法定相続人なら非課税 登録免許税:税率 0.4%(相続の場合) |
手続きと税金について

手続き
負担付死因贈与契約は口頭でも成立しますが、後のトラブルを防ぐために、必ず契約書を作成することが重要です。特に、贈与財産や負担の内容を具体的に明記する必要があります。
最も確実な方法は、公証役場で公正証書として作成することです。公正証書にしておくことで、契約の存在や内容が公的に証明され、不動産の登記手続きなどもスムーズに進めることができます。
税金
負担付死因贈与によって財産を取得した場合、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
ただし、不動産を取得した場合は注意が必要です。遺贈によって法定相続人が不動産を取得した場合にはかからない不動産取得税が課税されます。また、所有権移転登記の際に必要となる登録免許税の税率も、相続の場合に比べて高くなります。
ご検討の際の注意点
負担付死因贈与契約は、贈与者の生前の希望を実現し、受贈者の権利を保護できる有効な手段ですが、一度契約すると安易に撤回できないという拘束力も持ち合わせています。また、他の相続人の遺留分を侵害するような内容の契約は、将来の紛争の原因となり得ます。
契約を検討する際は、そのメリット・デメリットを十分に理解し、税金面の違いも考慮した上で、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。


