日本の多くの会社員にとって、老後の生活を支える大切な柱の一つである退職金。しかし、2024年の税制改正によって、その退職金にかかる税金が大きく変わるかもしれません。特に注目されているのが、退職所得控除に関する「5年ルール」の変更です。今回は、この改正案があなたの退職金にどのような影響を与えるのか、分かりやすく解説します。
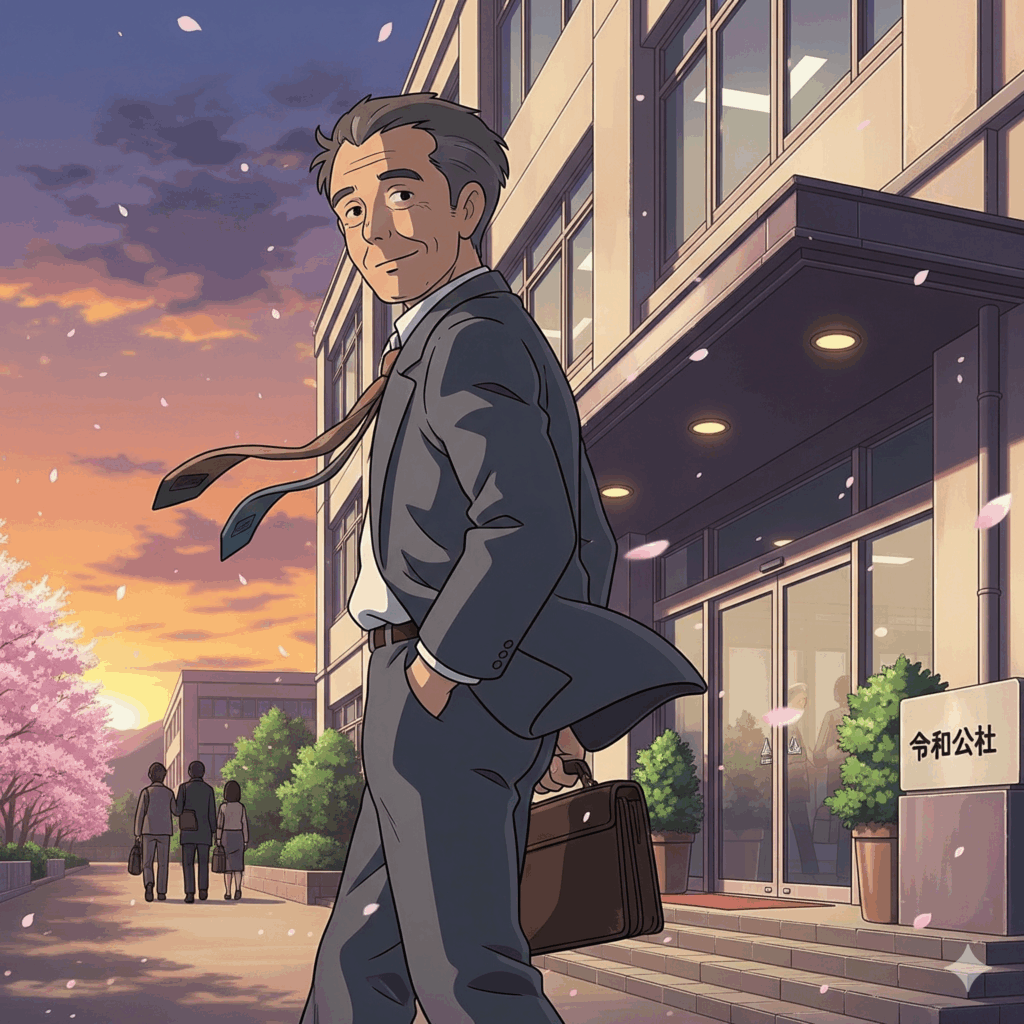
そもそも「退職所得控除」とは?
退職金は、退職後の生活資金を確保するために、税金面で優遇されています。この優遇制度が退職所得控除です。これは、勤続年数に応じて一定額まで非課税にするというもので、退職金から控除額を引いた残りの額に税金がかかります。
退職所得控除額は以下の計算式で求められます。
- 勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数
- 勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)
たとえば、勤続30年の場合、控除額は「800万円 + 70万円 × (30年 – 20年) = 1,500万円」となります。もし退職金が1,500万円以下であれば、税金はかからないことになります。
なぜ「5年ルール」が問題視されている?
これまでの税制では、勤続年数が5年以下の退職者に対して、退職金の税金を計算する際に、控除後の金額を半分にするという優遇措置がありませんでした。つまり、勤続年数が5年超の人に比べて、税金の負担が大きくなっていました。これは、短期での退職を繰り返す、いわゆる「ジョブホッパー」への税制上のペナルティとも言えます。
しかし、一部の経営者や役員は、このルールを悪用していると指摘されていました。彼らは、退職金を「役員退職金」と「功労金」などに分割し、勤続年数を操作することで、退職金全体の税負担を軽くする節税を行っていました。
注目すべき税制改正「5年ルール→10年ルール」
この抜け穴を塞ぐために、今回の税制改正案では、勤続5年以下の役員や従業員に対する退職所得の計算方法が見直され、優遇措置が縮小されることになりました。具体的な内容はまだ確定していませんが、現在議論されているのは、勤続10年以下の退職者に対する税制優遇の見直しです。
この変更が実現すれば、勤続10年以下の人が退職金を受け取る場合、これまでよりも税負担が重くなる可能性があります。特に、転職を繰り返すキャリア形成を考えている若い世代にとっては、退職金の受け取り方がより重要になります。
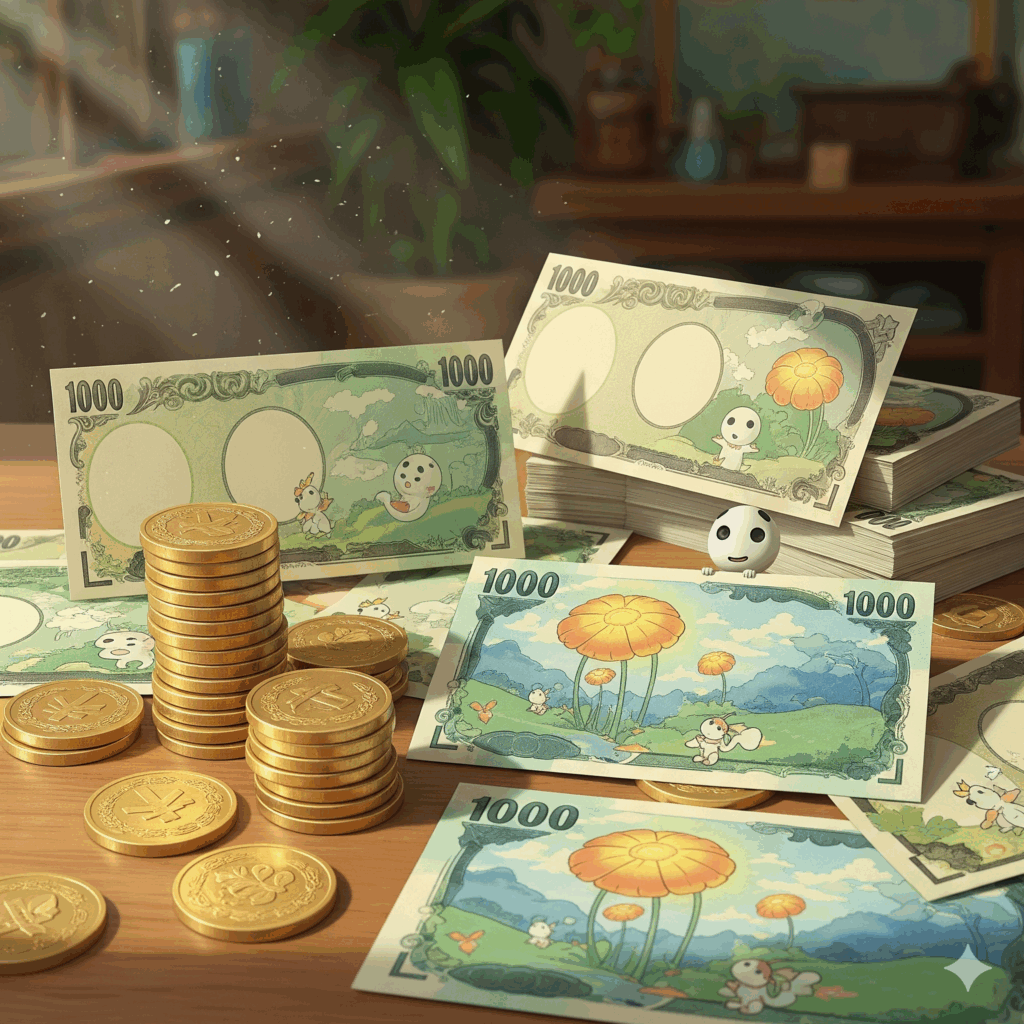
💰 実際の計算例を見てみよう
では、この変更によってどれくらい税金が増えるのか、具体的な例を見ていきましょう。
【条件】
- 退職金:1,500万円
- 勤続年数:10年
- 退職所得控除額:40万円 × 10年 = 400万円
1. 改正前の計算(5年ルール)
- 退職所得の課税対象額 (1,500万円 – 400万円) ÷ 2 = 550万円
- 所得税額 550万円に対する所得税・住民税を計算します。 ここでは簡略化のため、所得税率を20%、住民税率を10%と仮定します。 (550万円 × 20%) + (550万円 × 10%) = 110万円 + 55万円 = 165万円
2. 改正後の計算(10年ルール)
- 退職所得の課税対象額 まず、退職金から退職所得控除を引きます。 1,500万円 – 400万円 = 1,100万円次に、この1,100万円を「300万円以下の部分」と「300万円を超える部分」に分けます。
- 300万円以下の部分: 300万円 ÷ 2 = 150万円
- 300万円を超える部分: 1,100万円 – 300万円 = 800万円
- 所得税額 950万円に対する所得税・住民税を計算します。 (950万円 × 20%) + (950万円 × 10%) = 190万円 + 95万円 = 285万円
3. 税額の差額
285万円(改正後) – 165万円(改正前) = 120万円
なんと、今回の変更により、120万円も税金が増えてしまう可能性があるのです。
最後に… 😟
今回の税制改正は、特に短期で転職を繰り返す人や、勤続年数5年〜10年で退職する人に大きな影響を与えます。
退職金は、老後の生活を支える大切な資金です。今回の変更点をしっかり理解し、今後のライフプランを考える上で参考にしてくださいね。
皆さんの働き方や退職金制度について、ご意見やご質問があれば、ぜひコメント欄で教えてください!


