遺言書が無効になる3つのパターンとトラブル回避策 📜
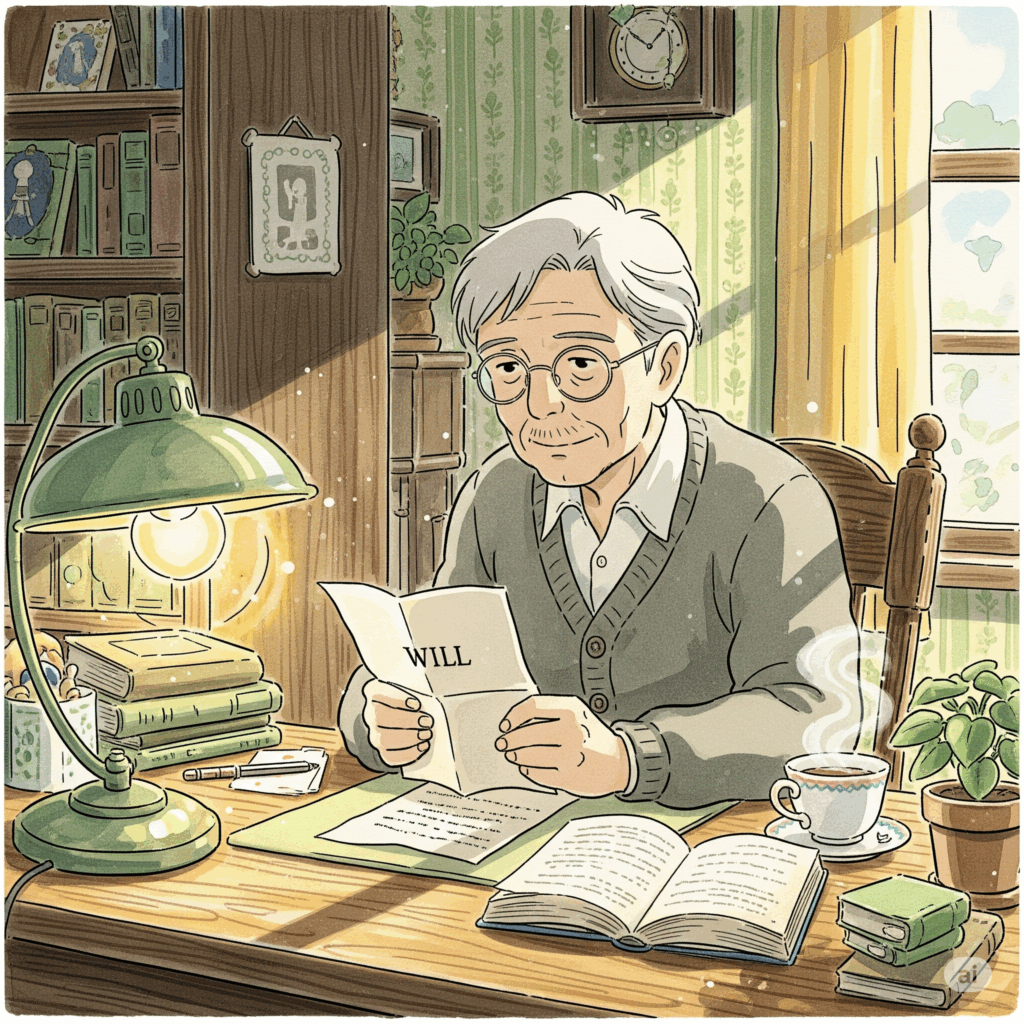
「遺言書を作成したから安心だ」と思っていませんか?実は、書き方を間違えたり、特定の条件を満たしていなかったりすると、せっかく作った遺言書が無効になってしまうことがあります。この記事では、遺言書が無効になる主な3つのパターンとそのトラブルを避けるためのポイントをわかりやすく解説します。
1. 方式不備による無効
遺言書には、法律で定められた厳格な作成方式があります。この方式を守らないと、遺言書全体が無効と判断されてしまいます。
- 自筆証書遺言の場合: 全文、日付、氏名を自筆で書く必要があります。パソコンや代筆は認められません。また、押印も必須です。
- 公正証書遺言の場合: 証人2人以上の立ち会いが必要で、証人が欠けていると無効になります。
2. 意思能力の欠如による無効
遺言書を作成した時に、本人の意思能力がなかったと判断されると、遺言書は無効になります。認知症などで判断能力が低下している状態で作成された遺言書は、後々トラブルの元になりがちです。
3. 内容の不明確さによる無効
誰に何を相続させるのかが不明確だと、遺言書の内容は無効になる可能性があります。「長男に財産を」とだけ書かれても、どの財産をどれだけ渡すのかが不明瞭だと解釈が分かれてしまい、トラブルに発展します。
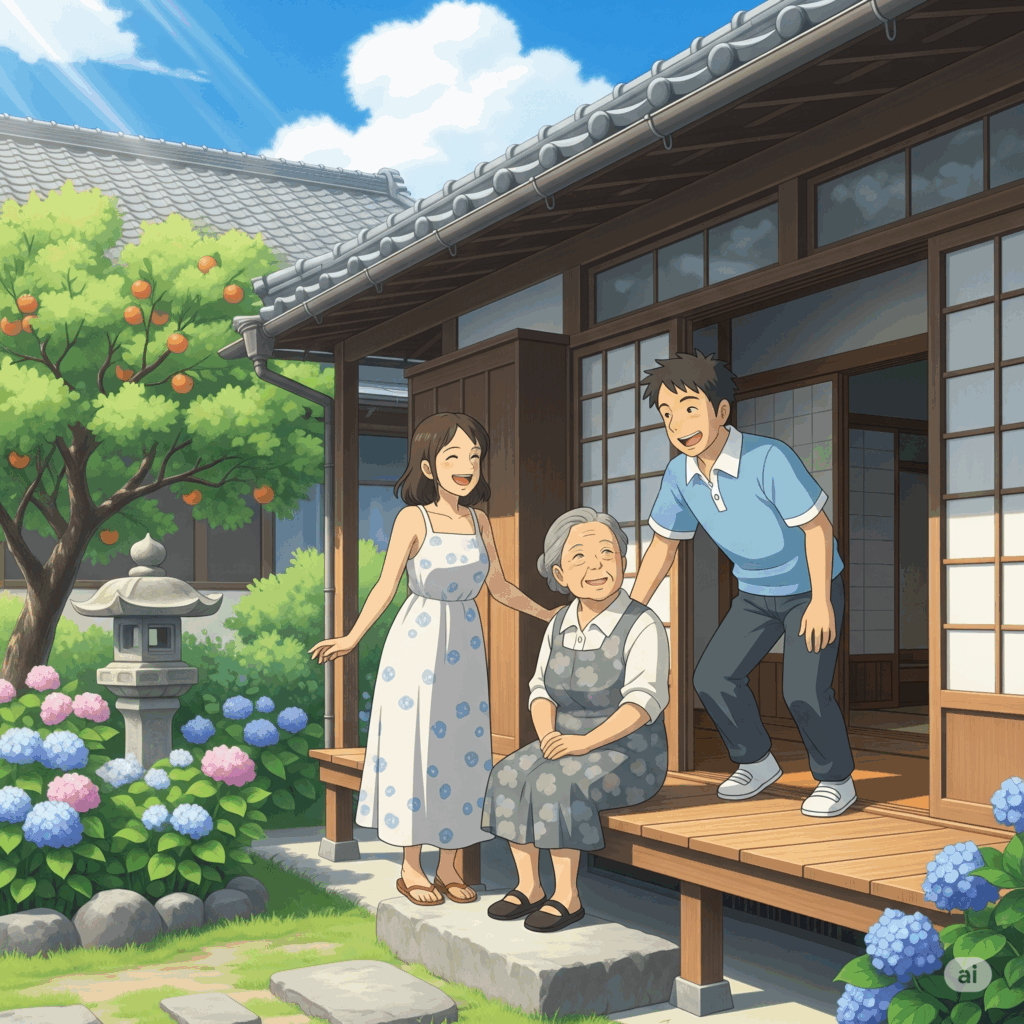
遺言書の安全性を高めるには?
遺言書が無効になるリスクを避けるために、以下の2つの方法が有効です。
公正証書遺言の活用
公正証書遺言は、公証役場で作成される公的な文書です。公証人が関与して作成されるため、方式不備による無効のリスクはほぼありません。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配も不要です。
しかし、「公正証書遺言には落とし穴がないのか?」と心配される方もいるかもしれません。公正証書遺言の無効の落とし穴として考えられるのは、作成時の意思能力の欠如です。たとえ公正証書であっても、本人の意思能力が著しく低い状態で作成された場合、後から無効を主張される可能性があります。
遺言書の開封と検認手続きの落とし穴
遺言書を見つけたからといって、勝手に開封してはいけません。特に、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。
検認とは?
検認は、遺言書が偽造・変造されていないかを裁判所が確認し、現状を保全する手続きです。検認を経ずに勝手に開封すると、5万円以下の過料に処される可能性があります。また、検認の手続き中に、他の相続人から遺言書の有効性について異議を唱えられ、トラブルに発展することもあります。
自筆証書遺言の検認とトラブル
自筆証書遺言の検認では、遺言書が本人の筆跡であるか、日付や氏名が正確に記載されているかなどが確認されます。この時、少しでも不備があると他の相続人から無効を主張される原因となります。
遺留分を減らすための賢い方法
遺言書を作成する際、特定の相続人に多くの財産を相続させたいと考えている方もいるでしょう。しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という、最低限の相続分が保証されています。遺留分を侵害する内容の遺言書は、後々遺留分侵害額請求の対象となり、トラブルになります。
遺留分トラブルを避けるために、以下の方法が考えられます。
1. 生前贈与の活用
特定の相続人に生前に財産を贈与しておくことで、遺産総額を減らすことができます。ただし、相続開始前1年以内の贈与は、遺留分の算定に含められる可能性があるため注意が必要です。
2. 生命保険の活用
生命保険は、受取人を指定することで、保険金は受取人固有の財産となり、原則として遺留分の対象になりません。これは遺留分対策として非常に有効な手段です。特定の相続人に多額の財産を残したい場合、生命保険の受取人にその人を指定する方法が効果的です。
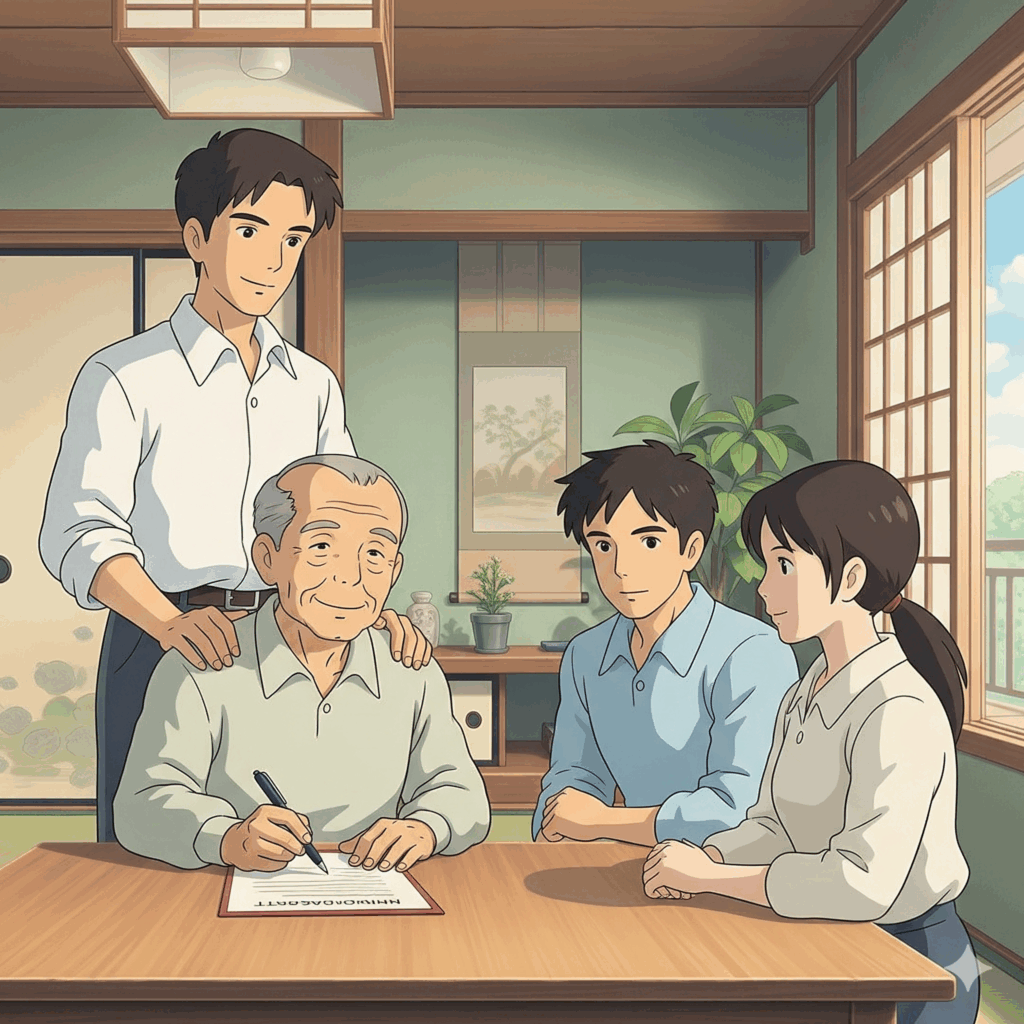
遺言書の保管方法と法務局保管制度のメリット
遺言書を安全に保管する方法として、遺言書の法務局保管制度があります。
遺言書は全て手書き?
いいえ、遺言書は全て手書きでなくても大丈夫です。2020年からは、自筆証書遺言の財産目録については、パソコンでの作成やコピーの添付が認められるようになりました。ただし、財産目録以外の本文、日付、氏名については依然として手書きが必要です。
遺言書の法務局保管制度とは?
この制度を利用すると、自筆証書遺言を法務局が保管してくれます。この制度の大きなメリットは以下の3点です。
- 紛失・偽造・改ざんのリスクがない
- 検認手続きが不要(法務局が原本を保管しているため、検認が不要となります)
- 他の相続人への通知(死亡後、遺言書の存在が相続人に通知されます)
この制度を利用することで、自筆証書遺言の信頼性を高め、スムーズな相続手続きにつながります。
遺言書は「書いて終わり」ではありません。トラブルなく、大切な人に思いを伝えるためにも、作成後の保管や手続き、そして遺留分への配慮が不可欠です。専門家への相談も視野に入れ、納得のいく遺言書作成を目指しましょう。


