「実家を相続したいけれど、自分は持ち家がなく賃貸暮らし。それでも土地の評価額を80%も減額してくれる『小規模宅地等の特例』は使えるのだろうか?」

そんな疑問をお持ちの方にとって、知っておくべきなのが「家なき子特例」です。
正式名称を「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人に配偶者がなく、かつ、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(法定相続人)がいなかった場合」といい、特定の条件下で、被相続人と同居していなかった親族でも「小規模宅地等の特例」の適用を認める制度です。
しかし、その名前のインパクトとは裏腹に、適用要件は非常に厳格で複雑です。一つでも要件を満たせないと、相続税額が何倍にも跳ね上がる可能性があります。
この記事では、「家なき子特例」の適用を目指す方が知っておくべき全ての要件を、一つひとつ詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
◆ 「家なき子特例」が生まれた背景
まず、なぜこのような特例が存在するのでしょうか。 「小規模宅地等の特例」は、残された家族が住む場所を失わないように、生活の基盤となる自宅土地の相続税負担を軽減することを目的としています。
そのため、基本的には被相続人の配偶者や同居していた親族が対象です。しかし、それでは天涯孤独の被相続人から実家を相続した、持ち家のない親族が、高額な相続税のために実家を手放さざるを得ないケースが出てきてしまいます。
こうした状況を救済するために、一定の厳しい条件のもとで、別居の親族にも特例の適用を認める「家なき子特例」が設けられました。
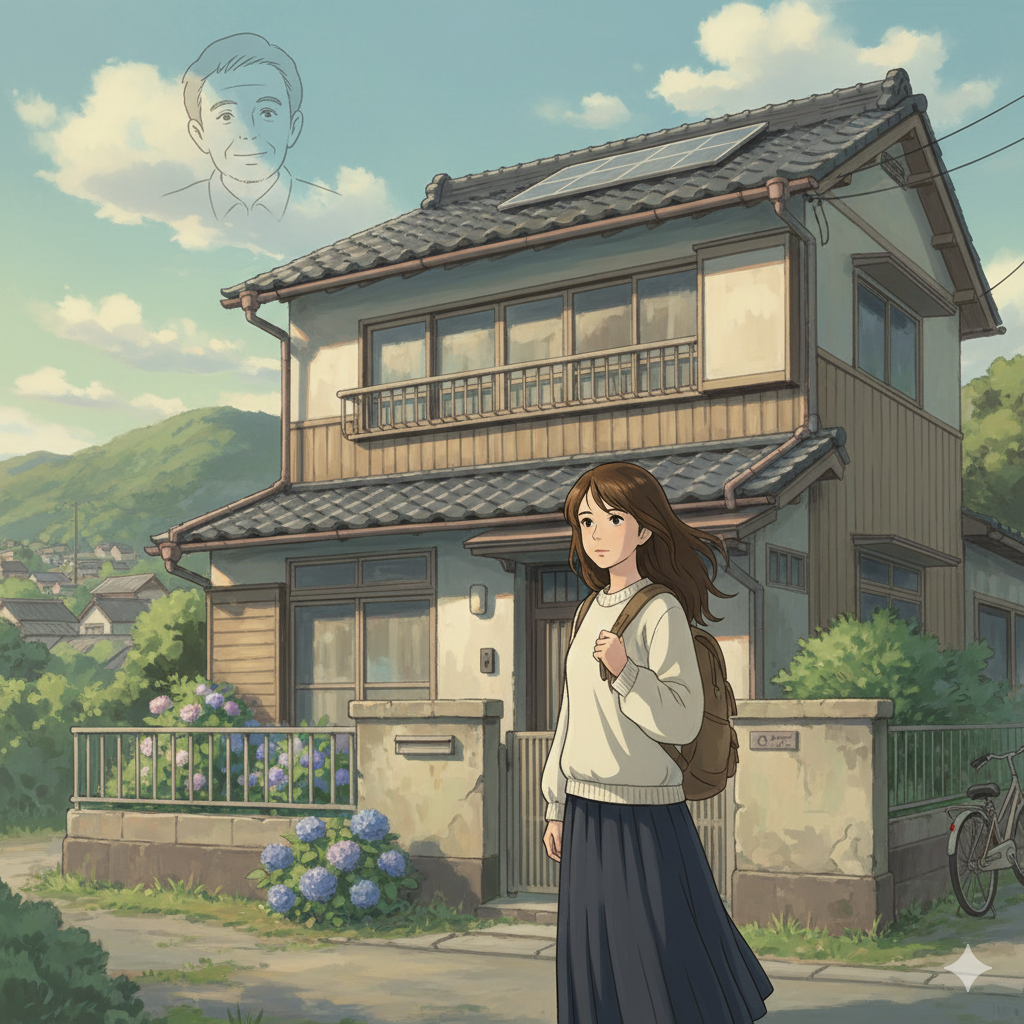
◆【最重要】家なき子特例の厳格な7つの適用要件
家なき子特例の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると適用は受けられません。
1. 被相続人に配偶者がいないこと
亡くなった方(被相続人)に、法律上の配偶者がいないことが絶対条件です。内縁関係のパートナーがいたとしても、戸籍上の配偶者がいなければこの要件は満たします。
2. 相続開始の直前に、同居の法定相続人がいないこと
被相続人が亡くなったときに、その家に同居していた法定相続人が一人もいないことが必要です。例えば、被相続人と同居している子が一人でもいる場合は、別居している他の子が実家を相続しても、家なき子特例は使えません。
3. 土地の取得者が、被相続人の親族(法定相続人)であること
特例の対象となるのは、民法で定められた相続人に限られます。
4. 相続開始前3年以内に、日本国内にある「自己または配偶者」の持ち家に住んだことがないこと
これが最も厳しく、解釈が難しいとされる「3年ルール」です。 相続人自身だけでなく、その配偶者が所有する家に住んでいた場合も対象外となります。例えば、3年以内に夫名義の家に住んでいた妻は、この要件を満たせません。あくまで賃貸物件や社宅などに住み続けている必要があります。
5. 相続開始前3年以内に、日本国内にある「3親等内の親族」または「特別な関係にある法人」の持ち家に住んだことがないこと
この要件も非常に重要です。たとえ自分の持ち家でなくても、親や祖父母、兄弟などが所有する家に住んでいた場合、特例は使えません。 例えば、親名義の実家を出て一人暮らしを始めたが、1年前に祖父名義のマンションに引っ越した場合などは、この要件に抵触します。
6. 相続した土地・家屋を相続税の申告期限まで所有し続けていること
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月です。この期限が来る前に、相続した土地や家を売却してしまうと特例は受けられません。
7. 相続開始時に住んでいる家を、過去に一度も所有したことがないこと
これは少し特殊な要件です。例えば、過去に住んでいた持ち家を売却し、相続開始時点では賃貸に住んでいたとしても、この要件を満たせないため特例の対象外となります。一度でも自分の家を持ってしまうと、生涯この要件はクリアできなくなります。
◆ よくある質問と注意点
Q1. 単身赴任で一時的に賃貸に住んでいる場合は?
A1. 住民票を移していても、生活の拠点が生計を共にする配偶者の住む持ち家にあると判断されれば、特例は適用されない可能性が高いです。税務署は生活の実態で判断します。
Q2. 3年以内に住んでいた持ち家が、共有名義の場合は?
A2. たとえ持分がごく僅か(例:1%)であっても、「自己の所有する家屋」とみなされ、特例の対象外となります。
Q3. 二世帯住宅の場合はどうなる?
A3. 建物の構造や登記の状況によって判断が分かれます。例えば、登記が区分登記(各世帯が独立)されている場合、親世帯に同居の親族がいないと判断され、別居の子が家なき子特例の対象となる可能性があります。一方、共有登記の場合は「同居」とみなされることが多く、専門的な判断が必要です。
◆ まとめ:計画的な準備が不可欠
「家なき子特例」は、その名の通り「持ち家を持たない子」を救済するための制度ですが、見てきたように、その適用条件は非常に厳格です。特に「3年ルール」は、知らず知らずのうちに抵触してしまっているケースも少なくありません。
ご自身がこの特例の対象となりうるのか、また、将来的にこの特例の活用を視野に入れるのであれば、ご自身の居住形態や親族の状況を正確に把握しておくことが重要です。
相続はいつ発生するか分かりません。いざという時に慌てないためにも、少しでも疑問や不安な点があれば、相続に強い税理士などの専門家に事前に相談し、最適な対策を講じておくことを強くお勧めします。


