夫婦間の相続で最大活用!「配偶者の税額軽減」の基礎知識
相続税の計算において、配偶者がいる場合の大きな柱となるのが「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。これは、配偶者の今後の生活保障や、夫婦の財産形成への寄与を考慮し、税の負担を大きく軽減するための制度です。

1. 配偶者の税額軽減とは?
配偶者が実際に相続した財産について、以下のいずれか多い金額までは相続税がかかりません(無税となります)。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、最低でも1億6,000万円までは、配偶者が相続する分には税金がかからないということです。
2. 控除額を超えるケースの例題
では、この1億6,000万円の控除額を超えた場合、どのように税金がかかるのでしょうか?
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 遺産総額 | 2億5,000万円 | 基礎控除後の課税遺産総額とします |
| 相続人 | 妻(配偶者)、子1人 | 法定相続分:妻1/2、子1/2 |
| 実際の遺産分割 | 妻:2億円、子:5,000万円 | 妻が多めに相続 |
このケースで、妻が相続する2億円にかかる相続税を見てみましょう。
| 項目 | 計算 | 結果 | 備考 |
| 妻の相続税の課税価格 | 2億円 | ||
| 配偶者の税額軽減額 | 1億6,000万円 | 1億6,000万円までは無税 | |
| 軽減後の課税対象額 | 2億円 – 1億6,000万円 | 4,000万円 | この4,000万円に対して税金がかかります |
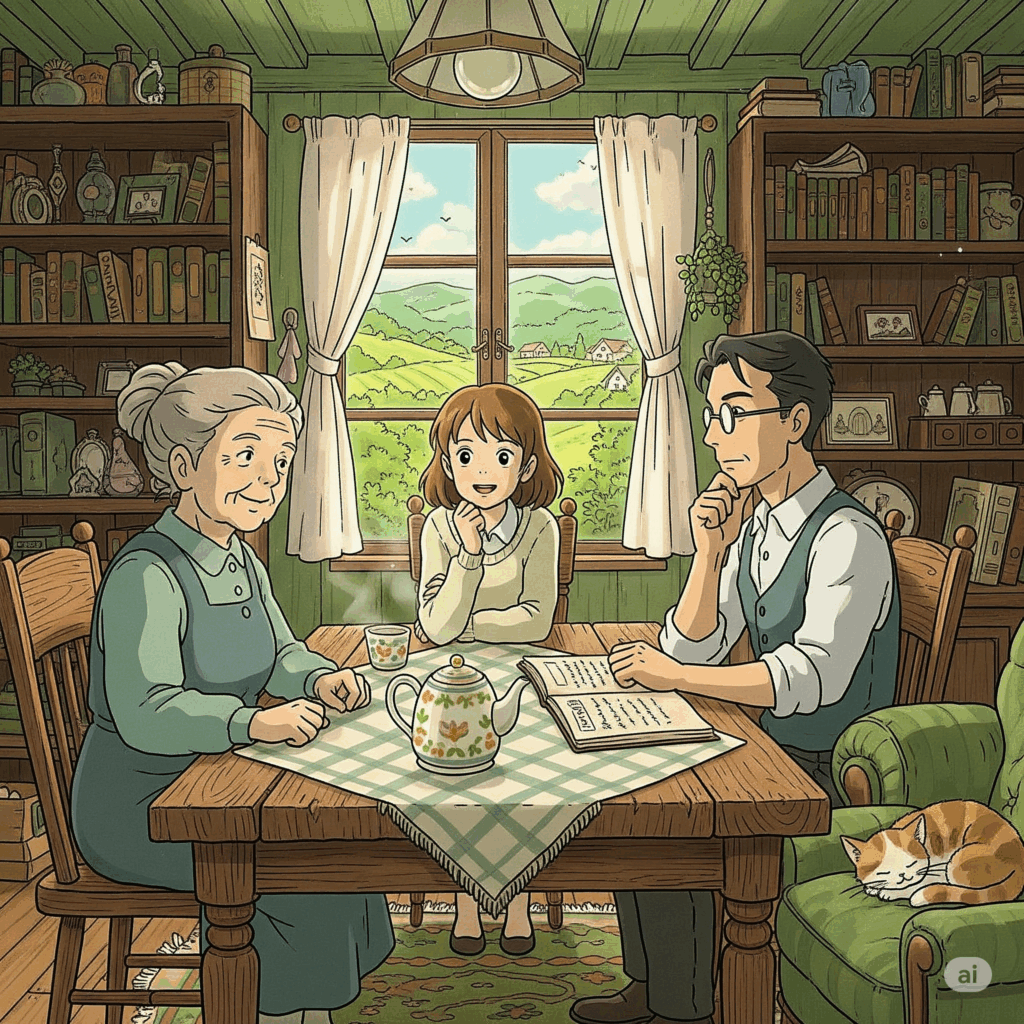
相続税対策の最重要ポイント:二次相続まで考えましょう
「配偶者の税額軽減」は強力な制度ですが、一次相続(夫や妻が亡くなった時の相続)で使いすぎると、二次相続(残された配偶者が亡くなった時の相続)でかえって税負担が重くなることがあります。
相続税のトータルコストを抑えるためには、一次相続と二次相続を合わせたトータルで税額を最小化することを考える必要があります。
1. 二次相続で相続税が割高になるケース
二次相続で相続税が割高になりやすいのは、主に以下の2つの理由からです。
理由①:基礎控除額が減る
相続税には基礎控除があり、遺産総額から控除できます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
| 相続 | 法定相続人 | 基礎控除額(例:子1人の場合) |
| 一次相続 | 配偶者+子 | 3,000万円+(600万円×2人) = 4,200万円 |
| 二次相続 | 子のみ | 3,000万円+(600万円×1人) = 3,600万円 |
二次相続では法定相続人から配偶者がいなくなるため、基礎控除額が減少し、課税対象となる遺産が増えます。
理由②:相続人の数が少ないと税率が上がる
相続税は、法定相続分で分けたと仮定した1人あたりの課税価格に応じて税率が適用され、その合計額を納税します。相続人が少ないほど、1人あたりの課税価格が高くなり、高い税率が適用されやすくなります。
| 相続 | 相続人 | 1人あたりの課税額 | 適用されやすい税率 |
| 一次相続 | 配偶者+子 | 分散される | 低い |
| 二次相続 | 子のみ | 高くなる | 高い |
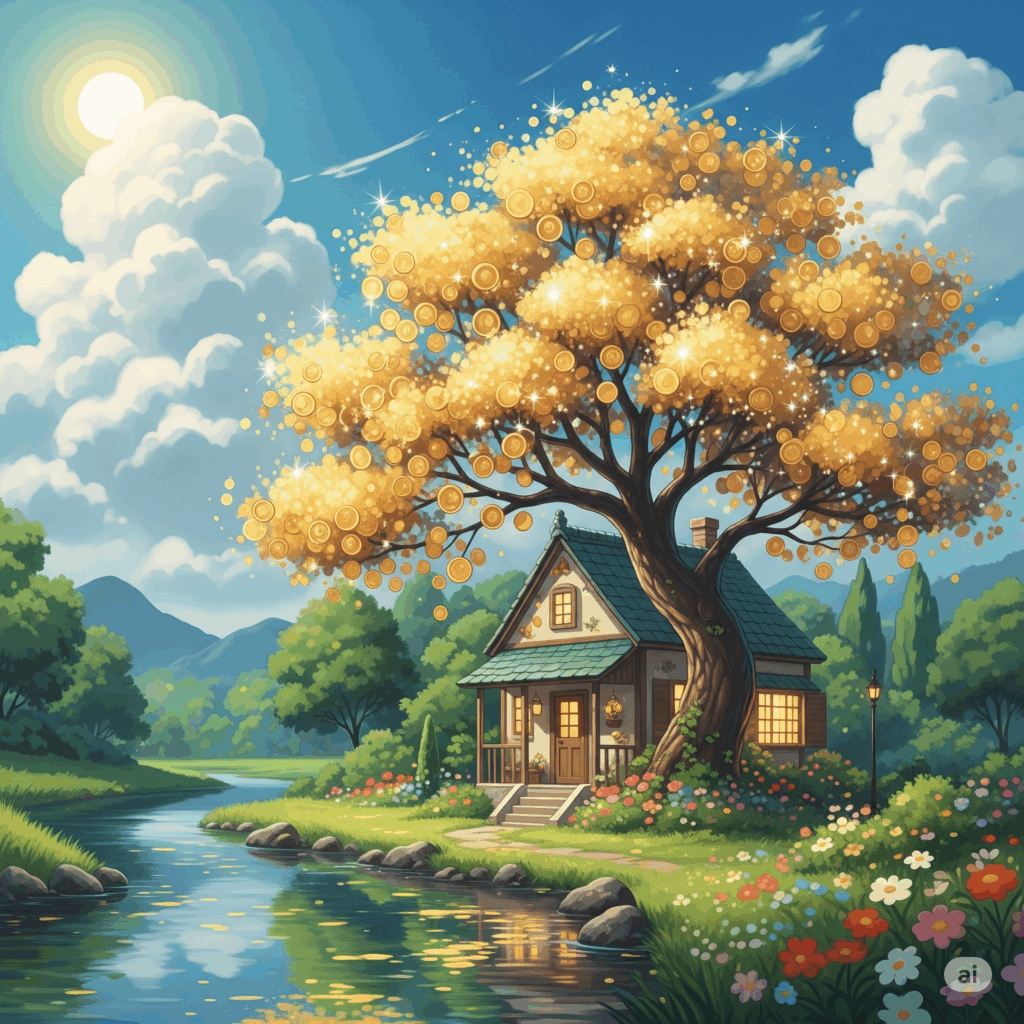
遺産の「賢い」分け方:二次相続を見据えた分割計画
相続税対策の結論として、夫婦間でどのくらい相続すべきかは、配偶者の生活資金の確保と二次相続の税負担軽減のバランスで決定されます。
1. 詳細に検討すべき2つのポイント
遺産分割計画を立てる際には、以下の2つの視点を詳細に検討しましょう。
① 被相続人の配偶者の今後から死亡時までの生活に必要な金額
配偶者の今後の生活資金は、税金対策以上に重要な考慮点です。
- 生活費の確保: 配偶者が残りの人生を不自由なく暮らせるだけの資金(毎月の生活費、医療費、介護費など)を算出し、配偶者が確実に相続します。
- 「小規模宅地等の特例」の活用: 配偶者が居住している自宅の土地は、一定の要件を満たせば80%評価減となり、大きな節税効果があります。これは配偶者に相続させるのが定石です。
② 配偶者の死亡後に残った財産の子供にかかる税金(二次相続)
配偶者の生活資金を確保した上で、「残った財産をいかに減らすか」「どれだけ一次相続で子に分けるか」を考えます。
| 対策の視点 | 具体的なアクション | 目的 |
| 一次相続時の分散 | 生活資金・特例適用分を除いた財産は、一次相続で子にも一定額を相続させる。 | 二次相続財産の圧縮と、相続人の分散による高税率の回避。 |
| 二次相続対策 | 配偶者が相続した財産から、生前贈与(年間110万円の非課税枠など)を行う。 | 二次相続時の財産を減らし、基礎控除や税率の不利を軽減する。 |
| 生命保険の活用 | 配偶者を契約者・受取人、子を契約者・受取人とする生命保険を活用する。 | 死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用し、二次相続の課税財産を減らす。 |
結論:最適な相続割合はケースバイケース
最も影響が大きく、大事な結論は以下の通りです。
- 配偶者の生活に必要な生活資金や居住用不動産は「配偶者の税額軽減」を利用して相続させ、配偶者の生活を第一に確保する。
- 配偶者の生活資金以上の財産については、一次相続時に子にも分けておくことで、二次相続時の基礎控除の減少と高税率の適用を避け、トータルの相続税負担を軽減する。
この最適な分割割合は、遺産総額、法定相続人の人数、配偶者の余命予測(あくまで概算)、生活費などによって大きく変わります。必ず専門家であるクレインに相談し、シミュレーションを行うことが、「賢い」相続の第一歩です。
ブログ読者の方へ:あなたの家庭の最適な相続計画について、さらに具体的なシミュレーションにご興味はありますか?それとも、生前贈与など他の相続対策について知りたいですか?


