「子どもの夢を応援したい」「少しでも早く財産を渡してあげたい」。そんな親心から行われる生前贈与。しかし、その親心が、残された家族の間で深刻な相続トラブル(争続)の火種になるケースが後を絶ちません。
今回は「生前贈与は遺産の先送り」というテーマについて、具体的な事例をもとに、相続で揉めないための重要なポイントを分かりやすく解説します。
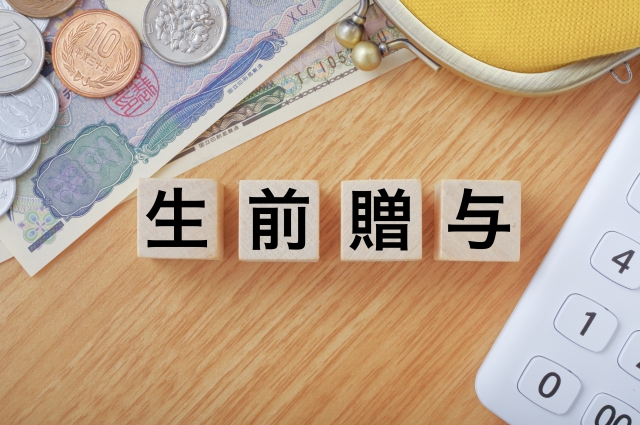
あなたの家族は大丈夫?ありがちな相続トラブルの事例
ここに、ごく普通の家族がいます。
- 父(67歳): 先日、病気で他界
- 母(65歳): 夫を亡くし、悲しみに暮れている
- 長男(37歳): 既婚。数年前に父から住宅購入資金として500万円の援助を受けた。
- 長女(30歳): 独身。数年前に父から海外留学の費用として300万円の援助を受けた。
父が残した財産は7,000万円。 父の死後、遺産分割協議が始まりましたが、話は思わぬ方向へ。
長女「お兄ちゃんは500万円ももらったんだから、その分、お母さんと私の相続分を多くすべきよ!」 長男「何を言うんだ。あれは親父が俺の家庭を応援してくれたお金だ。遺産とは別だろう!お前だって留学費用を出してもらっていたじゃないか!」
良かれと思ってした生前の援助が、兄妹の溝を深める原因となってしまいました。なぜ、このような事態に陥ってしまったのでしょうか。その鍵を握るのが「特別受益」という考え方です。
揉め事の根本原因「特別受益」とは?
特別受益とは、簡単に言えば「被相続人(亡くなった方)から生前に受けた、遺産の前渡しとみなされる利益」のことです。
相続では、相続人の中に特別受益を受けた人がいる場合、その人が受け取った利益を一旦、相続財産に加算して(これを「持ち戻し」と言います)、その上で各相続人の取り分を計算します。これは、相続人間の不公平をなくすためのルールです。
長男の住宅購入資金や長女の留学費用は、この特別受益に該当する可能性が非常に高いのです。
どんな生前贈与が「特別受益」になる?
全ての生前贈与が対象となるわけではありません。扶養義務の範囲内で行われる生活費の援助や、少額のお祝い、お小遣いなどは通常、特別受益にはあたりません。
特別受益と判断されやすいのは、以下のような贈与です。
- 結婚や養子縁組のための持参金、支度金
- 独立開業資金、事業資金
- 住宅購入資金
- 高等教育の費用(特に他の兄弟との間に著しい差がある場合)
- 今回のケースでは、長女の留学費用も特別受益とみなされる可能性が高いでしょう。
「時効」はあるの?10年ルールに注意!
以前は、特別受益の持ち戻しに期間の定めはありませんでした。しかし、2019年の民法改正により、相続開始(死亡)前の10年間に行われた贈与が持ち戻しの対象として明確化されました。
つまり、何十年も前の贈与について「あれは特別受益だ!」と主張することが難しくなったのです。
【具体的に計算】もし、この家族が法律通りに分けるとしたら?
では、先ほどの例で、特別受益を考慮して遺産を計算してみましょう。
- みなし相続財産を計算する まず、生前贈与を遺産に足し戻します。 7,000万円(遺産) + 500万円(長男への贈与) + 300万円(長女への贈与) = 7,800万円 この7,800万円を「みなし相続財産」として、法定相続分で分けます。
- 法定相続分を計算する
- 母(配偶者): 1/2
- 長男(子): 1/2×1/2=1/4
- 長女(子): 1/2×1/2=1/4
- 各人の最終的な取得額を計算する
- 母: 7,800万円 × 1/2 = 3,900万円
- 長男: 7,800万円 × 1/4 = 1,950万円 ここから、すでに受け取っている500万円を差し引きます。 1,950万円 – 500万円 = 1,450万円
- 長女: 7,800万円 × 1/4 = 1,950万円 ここから、すでに受け取っている300万円を差し引きます。 1,950万円 – 300万円 = 1,650万円
このように、特別受益を考慮することで、相続人間の公平が図られます。しかし、これはあくまで法律上の計算。家族の感情的なしこりは、数字だけでは解決できないことも多いのです。
相続トラブルを避けるために、生前にできた対策は?
今回の事例で、家族は事前にどのような対策を打てたのでしょうか。それぞれの立場で考えてみましょう。
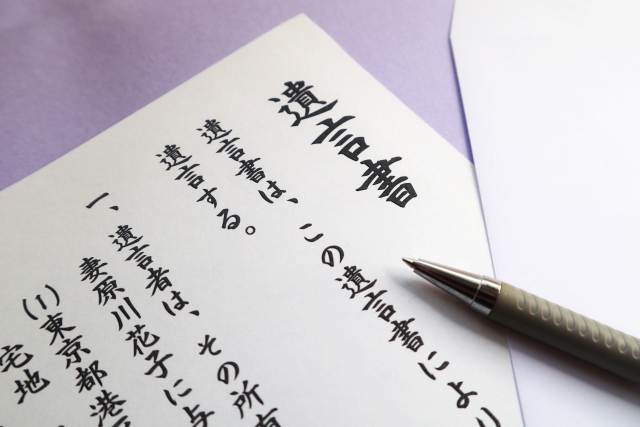
【父】ができたこと:明確な意思表示
- 遺言書で「持ち戻し免除の意思表示」をする これが最も重要かつ効果的な対策です。父が遺言書に**「長男への住宅資金500万円と長女への留学費用300万円は、遺産の前渡しではなく、私の特別な想いからの贈与であるため、遺産分割の際に持ち戻しを免除する」**と明確に記していれば、原則として特別受益の計算は不要になります。
- 想いを「付言事項」として残す 遺言書には、法的な効力はないものの、家族へのメッセージとして「付言事項」を残せます。「なぜそのような分け方をしたのか」「子どもたちにどう暮らしてほしいか」といった想いを綴ることで、残された家族の納得感を得やすくなります。
- 生命保険の活用 生命保険の死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象外です。例えば「長男と長女への生前贈与は特別受益として計算してもよい。その代わり、一番世話になった妻(母)に多めに現金を残したい」と考えるなら、母を受取人とする生命保険に加入しておくのも一つの手です。
【母】ができたこと:家族のコミュニケーションを促す
- 夫に遺言書の作成を勧める 「縁起でもない」とためらう気持ちは分かりますが、「残される家族のためよ」と夫に遺言書の作成を優しく促すことが、妻としてできる最大のサポートだったかもしれません。
- 家族会議を開く 生前贈与について、家族全員がオープンに話せる場を設けることも大切です。「あの時の援助は、お父さんのこういう想いからだったのよ」と、父の気持ちを代弁し、子どもたちの理解を求める役割も担えたでしょう。
【長男・長女】ができたこと:感謝と認識
- 「遺産の前渡し」である可能性を認識する 親から高額な援助を受ける際に、「これは将来の相続分の一部かもしれない」という認識を持つことが大切です。
- 親の意思を確認・記録する 援助を受ける際に「お父さん、この援助は将来の相続の時にどう考えればいい?」と尋ね、もし「遺産とは別だよ」と言われたのであれば、その旨を記した念書(持ち戻し免除の意思表示書)を書いてもらうことも、後のトラブル回避につながります。(ただし、親子関係で実行するのは難しい場合もあります)

知っておきたい関連ルール
自宅贈与は特別受益にならない?(おしどり贈与)
法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(マイホーム)の贈与または購入資金の贈与があった場合は、原則として「持ち戻し免除の意思表示」があったものと推定されることになりました。これにより、残された配偶者の生活が保護されやすくなりました。
逆のパターン「寄与分」
特別受益とは逆に、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人がいる場合、その貢献分を相続財産から確保できる「寄与分」という制度もあります。 例えば、「長女が仕事を辞めて無償で父の介護を長年続けた」「長男が家業を継ぎ、その給与が不当に安かった」などのケースが考えられます。寄与分が認められれば、その分多く遺産を受け取ることができます。
まとめ:最高の生前贈与は「準備」と「対話」
生前贈与は、子や孫の人生を力強く後押しする素晴らしい行為です。しかし、その善意が「争続」の火種にならないよう、贈与する側も受け取る側も、将来の相続を見据えた準備と対話が不可欠です。
- 贈与する側は、遺言書で意思を明確にすること。
- 家族全員で、お金の話をオープンにできる関係を築くこと。
少しでも不安を感じたら、クレインに相談することをお勧めします。元気なうちにしっかりと対策を講じることが、家族への一番の贈り物になるはずです。


