ご主人が亡くなり、残された奥様が自宅には住み続けられるものの、生活費に困ってしまうケースは少なくありません。 特に、お子さんがいる場合、遺産分割でもめることもあります。 このような状況を解決するために、2020年4月1日から「配偶者居住権」という新しい制度が始まりました。 この記事では、具体的な事例を交えながら、配偶者居住権の仕組みとそのメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
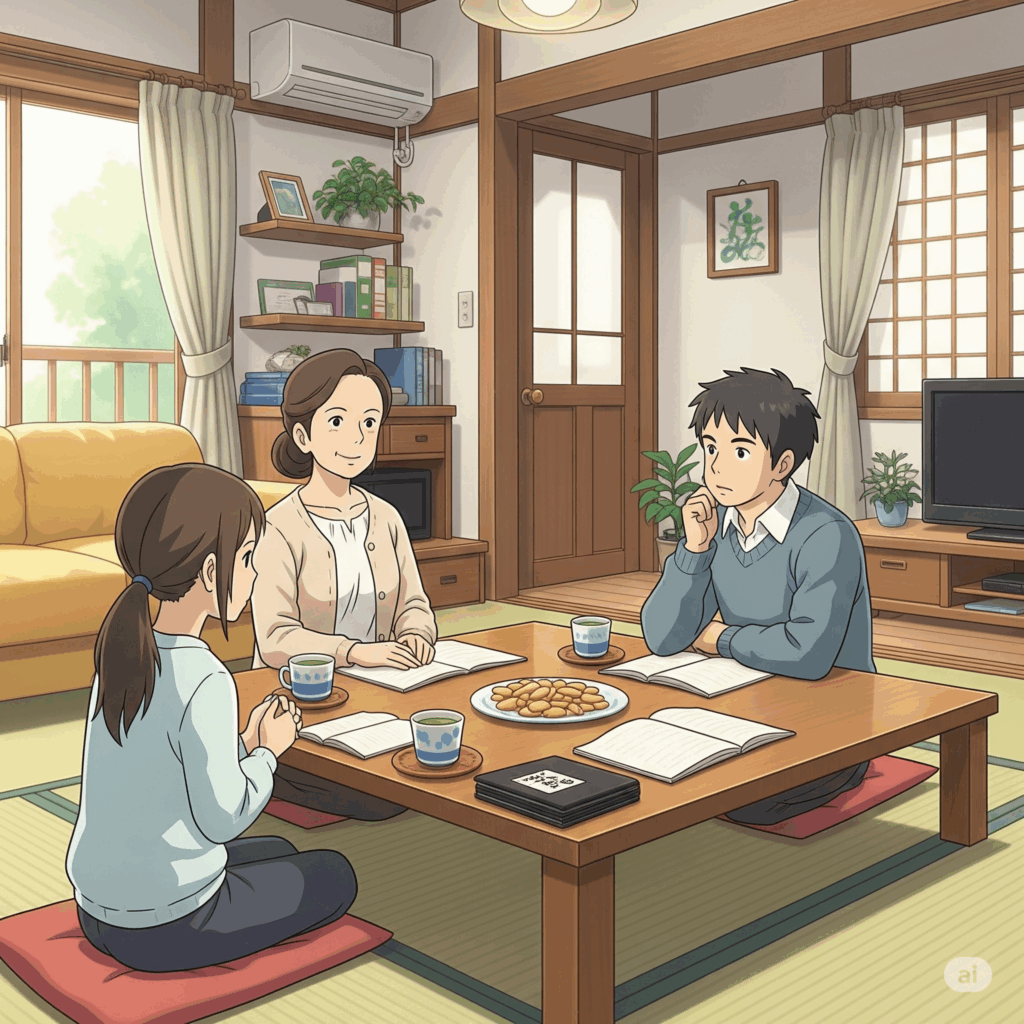
目次
- 母が自宅を相続したけど、生活費がない問題
- 配偶者居住権とは?
- 配偶者居住権の設定によるメリットとデメリット
- 母が亡くなったあとの、長男と長女の自宅の相続権に関する3つの方法
- 配偶者居住権のまとめ
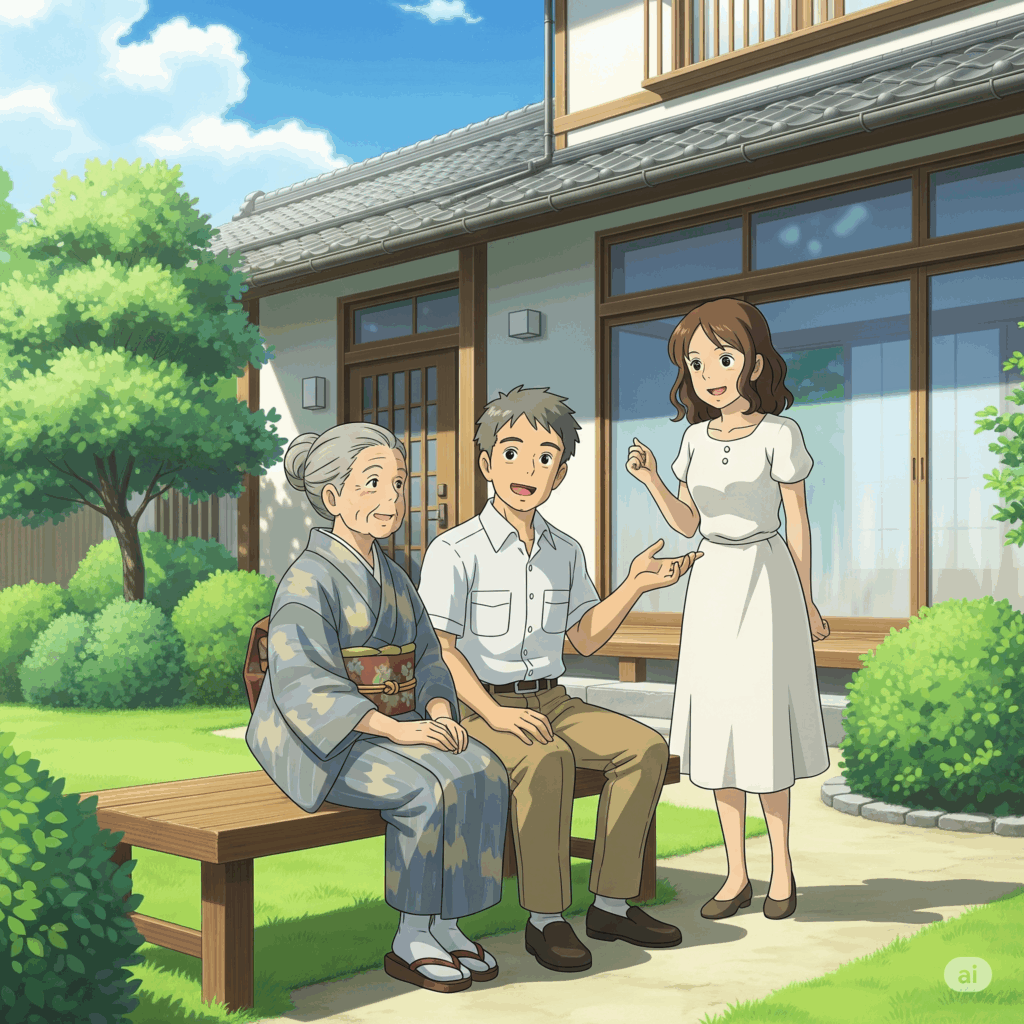
1. 母が自宅を相続したけど、生活費がない問題
あるご家庭の事例です。 夫が亡くなり、遺産は以下の通りでした。
- 相続財産: 3,500万円の現金預金と3,500万円の自宅(総額7,000万円)
- 相続人: 妻(母)、長男(51歳)、長女(40歳)
法定相続分は、妻が1/2、長男と長女がそれぞれ1/4です。 遺産分割協議で、長男と長女はこう主張しました。
「自宅(3,500万円)は母さんが相続するのだから、残りの現金3,500万円は、僕たちで半分ずつ相続させてほしい。つまり、長男1,750万円、長女1,750万円だね。」
この提案に、奥様は困惑します。 自宅を相続すれば、住む場所は確保できますが、生活費となる現金がほとんど手元に残りません。 年金だけでは不安な老後生活が待っています。
しかし、2020年4月以降であれば、この問題を解決できる「配偶者居住権」という選択肢があります。
2. 配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、残された配偶者が自宅に生涯または一定期間、無償で住み続けることができる権利のことです。 この権利は、遺産分割協議や遺言、家庭裁判所の審判で設定できます。
配偶者居住権を設定すると、自宅の所有権は他の相続人が取得し、自宅の評価額は「所有権」と「配偶者居住権」に分けて評価※1されます。 例えば、3,500万円の自宅の評価額が、所有権が1,500万円、配偶者居住権が2,000万円と分割されるイメージです。 この場合、奥様は2,000万円相当の「配偶者居住権」を取得し、残りの1,500万円の「所有権」をお子さんたちが取得します。
この仕組みを利用すれば、先ほどの事例は以下のように解決できます。
- 妻(母): 配偶者居住権(2,000万円相当)+現金預金1,500万円
- 長男: 現金預金1,000万円
- 長女: 現金預金1,000万円
- 長男・長女:所有権1,500万円
- 総額:7,000万円
この分割であれば、奥様は自宅に住み続けられ、さらに生活費となる現金も確保できます。 残された相続財産をめぐる争いを避け、円満な相続を実現するための有効な手段となります。
3. 配偶者居住権の設定によるメリットとデメリット
✅ メリット
- 居住権と現金を両立できる 自宅の所有権を放棄することで、その分の現預金を多く相続できます。 これにより、老後の生活資金を確保しながら、住み慣れた家で暮らし続けることが可能になります。
- 相続税対策になる可能性がある 配偶者居住権の評価額は、所有権の評価額よりも低くなることがあります。 これにより、遺産総額を下げ、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
❌ デメリット
- 登記が必要 配偶者居住権は登記しなければ第三者に対抗できません。 登記手続きには費用がかかります。
- 売却や賃貸に制限がある 配偶者居住権を設定すると、勝手に自宅を売却したり、誰かに貸したりすることができません。 自宅の売却が必要になった場合は、所有者の同意が必要になります。
- 家の修繕義務が生じる 配偶者居住権者は、自宅を維持管理する義務があります。 大規模な修繕やリフォームを行う場合は、所有者の同意が必要です。
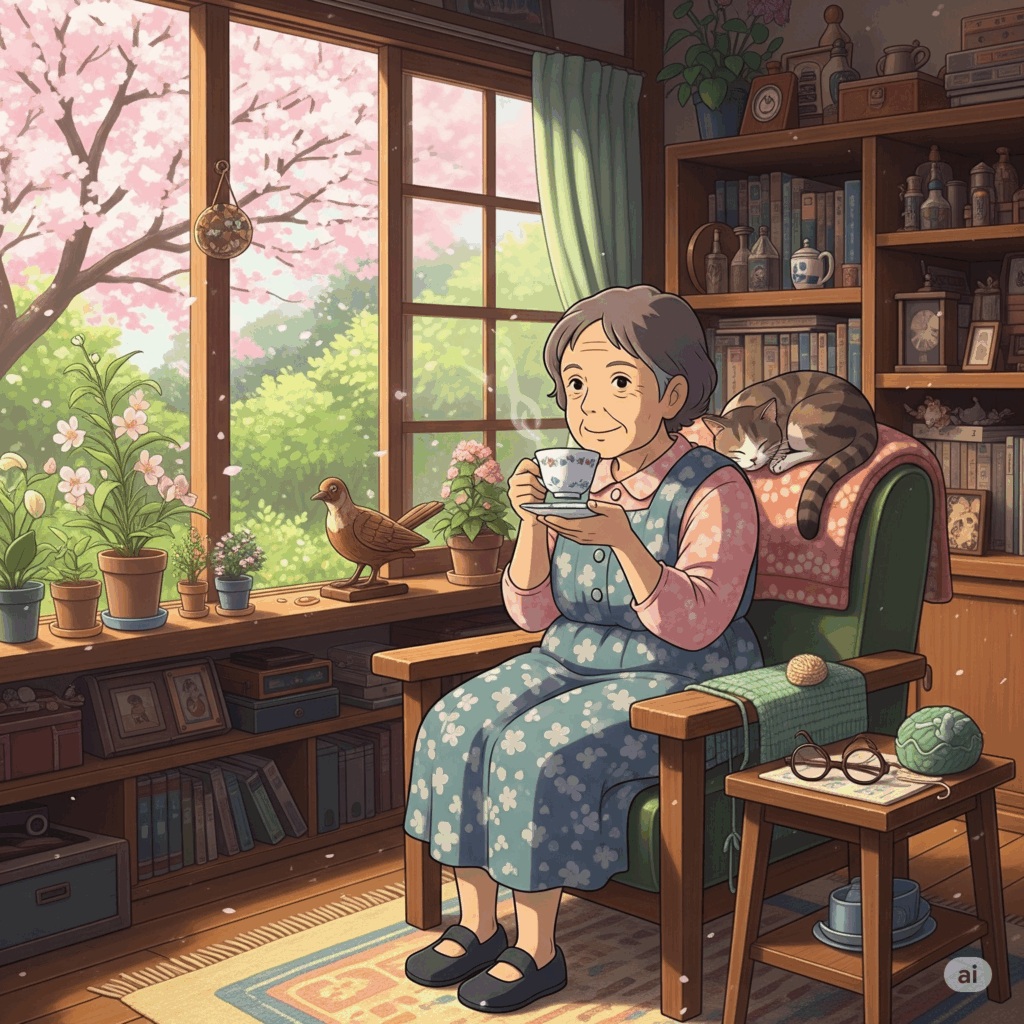
4. 母が亡くなったあとの、長男と長女の自宅の相続権に関する3つの方法
配偶者居住権が設定された自宅は、奥様が亡くなった後、どうなるのでしょうか? 奥様の死亡と同時に、配偶者居住権は消滅し、自宅の所有権は長男と長女のものとなります。 この自宅をどうするか、3つの方法があります。
1. 不動産の売却
最も一般的な方法です。 長男と長女が自宅を売却し、得た現金を分け合います。 この方法であれば、公平に財産を分割できます。
2. 配偶者居住権の設定
奥様が亡くなると同時に配偶者居住権は消滅しますが、遺言書や遺産分割協議により、長男や長女が配偶者居住権を設定することも可能です。 しかし、このケースは稀で、所有権を相続することがほとんどです。
3. 所有権の相続
長男と長女のどちらかが自宅の所有権を単独で相続し、もう一方に代償金を支払う方法です。 例えば、長男が自宅を相続し、長女に相当額の現金を支払います。 兄弟間の話し合いが不可欠であり、代償金を用意できるかどうかがポイントになります。
5. 配偶者居住権のまとめ
配偶者居住権は、残された配偶者が経済的に困窮することなく、住み慣れた自宅で安心して暮らせるようにするための画期的な制度です。 特に、自宅が主要な相続財産であり、現金預金が少ないケースで非常に有効です。 相続は、残された家族が協力して進めることが何より大切です。 配偶者居住権の活用も含め、専門家である税理士や弁護士に相談しながら、家族にとって最適な解決策を見つけましょう。
※1配偶者居住権を主張し、取得する方法は、主に以下の3つがあります。
1. 遺産分割協議で取得する
これが最も一般的な方法です。相続人全員(配偶者、子など)が話し合い、合意の上で、配偶者が自宅に住み続ける代わりに配偶者居住権を取得し、他の相続人が所有権を取得するという内容で遺産分割協議を成立させます。協議が成立したら、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。
2. 遺言書で指定してもらう
被相続人(亡くなった方)が、遺言書で配偶者に対して配偶者居住権を「遺贈」する旨を記載しておく方法です。これにより、遺言書の内容に従って、配偶者は配偶者居住権を取得できます。この方法は、遺産分割協議でのトラブルを避けるために有効です。
3. 家庭裁判所の審判で決めてもらう
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られない場合、配偶者は家庭裁判所に遺産分割の「審判」を申し立てることができます。審判では、裁判官が事情を考慮して、配偶者に配偶者居住権を取得させるかどうかの判断を下します。
💡ポイント:登記を忘れずに
配偶者居住権を取得した後は、不動産の登記簿にその旨を登記する必要があります。登記をしておかないと、自宅の所有権を取得した人が第三者に自宅を売却してしまった場合に、配偶者居住権を主張できなくなる可能性があるため、必ず行いましょう。


