【速報解説】2025年度税制改正大綱のポイント!私たちの生活はどう変わる?給与所得控除と子育て支援策をチェック
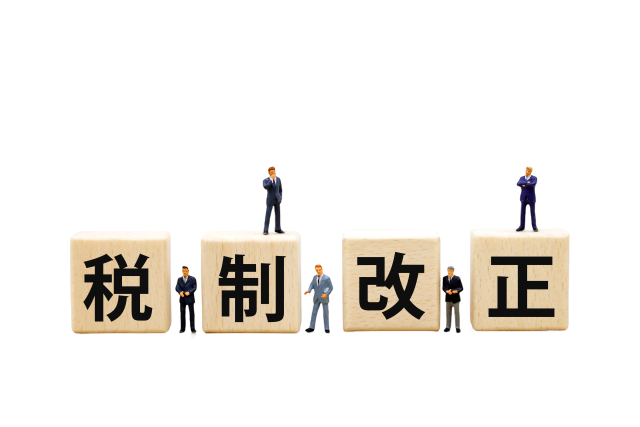
こんにちは!毎年この時期になると気になるのが税制改正の話題ですね。2025年度(令和7年度)の税制改正大綱でも、私たちの生活に直結するいくつかの重要な変更点が盛り込まれる見込みです。
特に注目したいのは、「給与所得控除の引き上げ」と「子育て支援のための税制優遇措置の拡充」です。これらが私たちの手取り収入や将来設計にどう影響するのか、そしてインフレに苦しむ家計にどのような効果をもたらすのか、詳しく見ていきましょう。
1.給与所得控除の引き上げ:手取りアップに繋がるか?
今回の改正で特に注目されるのが、給与所得者にとって重要な「給与所得控除」の見直しです。
主な変更点
- 最低保障額の引き上げ: 現行の55万円から65万円に10万円引き上げられます。 これは、特に収入が比較的低い層にとって、税負担の軽減に繋がります。
収入金額に応じた控除額の考え方
給与所得控除は、給与等の収入金額に応じて段階的に計算方法が定められています。今回の改正で最低保障額が65万円に引き上げられることを踏まえると、以下のようになります。
- 給与等の収入金額が190万円以下の場合の控除額
- これまでは、収入金額に応じて55万円が最低ラインでしたが、これが65万円に引き上げられます。
- 具体的には、現行制度(令和5年分以降)では、収入金額が162.5万円以下の場合の給与所得控除額は55万円です。今回の改正により、このラインが引き上げられ、例えば収入190万円の方の給与所得控除額は、結果として65万円になるように調整される見込みです。(詳細な計算テーブルは国税庁の発表をご確認ください。多くの場合、収入が190万円以下の方の控除額は一律65万円、もしくはそれに近い金額になるように設定されます。)
- つまり、収入が190万円以下の方であれば、多くの場合で給与所得控除額が65万円となる見込みです。
- 給与等の収入金額が190万円超の場合の控除額(具体的な計算式): 現行の給与所得控除の速算表をベースに考えると、収入金額が190万円を超える場合、多くは以下の計算式が適用される区分に入ってきます。 (注:以下の計算式は、改正後の正式な速算表が発表されるまでは現行制度を参考にしています。改正内容により変動する可能性があるため、あくまで目安としてください。) 収入金額が180万円超360万円以下の場合の計算式は、現行では「収入金額 × 30% + 8万円」です。 この計算式を190万円超のケースに適用すると、
- 例:給与等の収入金額が200万円の場合 控除額 = 200万円 × 30% + 8万円 = 60万円 + 8万円 = 68万円
- 例:給与等の収入金額が300万円の場合 控除額 = 300万円 × 30% + 8万円 = 90万円 + 8万円 = 98万円
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162.5万円超180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円以下超190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | |
表によらず所得税法別表第五により求めるとされていますので、
表の算式で求めた給与所得控除額とは異なる事があります。
2.子育て支援のための4つの改正点:家計への追い風に
少子化対策が急務とされる中、子育て世帯を支援するための税制改正も注目ポイントです。
- 住宅ローン控除の1年延長: 子育て世帯や若者夫婦世帯に対し、現行の住宅ローン控除(減税)の措置が1年間延長される見込みです。マイホームの購入やリフォームを検討している家庭にとっては朗報と言えるでしょう。
- リフォーム減税の1年延長: 子育てに対応したリフォーム(例:子供部屋の増設など)や省エネ改修など、特定の住宅リフォームに対する減税措置も1年間延長される方向です。より快適で安全な住環境を整えやすくなります。
- 子育て世帯の生命保険料控除拡大: 現行の生命保険料控除に加えて、扶養する子供がいる世帯に対して、生命保険料控除の枠が拡大される案が検討されています。子供の将来のための学資保険や万が一の備えとしての死亡保険など、保険料負担が軽減されることで、家計の安心感を高めます。
- 結婚・子育て資金贈与の非課税制度2年延長: 祖父母や親から結婚や子育てに必要な資金を贈与された場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度(現在は最大1,000万円)が、2年間延長される見込みです。教育資金や出産費用など、まとまった資金が必要となるライフイベントへの経済的支援が継続されます。
3.インフレに対応するためのポイントは?
今回の税制改正、特に給与所得控除の引き上げや各種子育て支援策は、物価上昇(インフレ)に直面する家計にとって、どのような意味を持つのでしょうか。
- 実質的な手取り収入の確保: 給与所得控除が引き上げられることで、課税所得が減り、結果として所得税・住民税が軽減されます。これは、昇給が物価上昇に追いつかない状況において、実質的な手取り収入を少しでも維持・向上させる効果が期待できます。
- 可処分所得の増加による消費マインドの改善: 手取りが増えれば、その分を消費や貯蓄に回す余裕が生まれます。特に、子育て関連の減税措置は、教育費や養育費など固定的な支出が多い子育て世帯の負担を和らげ、消費マインドの冷え込みを防ぐ一助となるでしょう。
- 特定支出への支援: 住宅ローン控除やリフォーム減税、生命保険料控除の拡充などは、特定の大きな支出や将来への備えに対する負担を軽減します。これにより、インフレ下でも必要な支出をためらうことなく行えるよう後押しする効果があります。
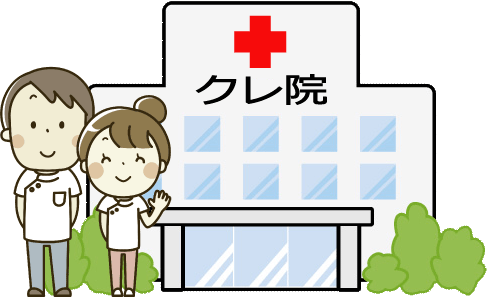
まとめ
2025年度の税制改正は、給与所得者や子育て世帯にとって、ささやかながらも家計を支える内容となりそうです。特に給与所得控除の最低保障額65万円への引き上げは、多くの方にとって減税効果が期待できます。
ただし、税制は非常に複雑であり、個々の状況によって影響は異なります。ご自身の具体的なケースについては、税理士などの専門家にご相談いただくか、国税庁や自治体から発表される正式な情報を必ず確認するようにしてください。
今回の改正が、少しでも皆さんの生活の安心に繋がることを願っています。
【免責事項】 この記事は、2025年度税制改正大綱に関する報道や公表情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。具体的な税務判断や申告については、税理士や税務署にご相談ください。内容の正確性については万全を期しておりますが、制度の変更等により情報が古くなる可能性もございますので、最新の情報をご確認ください


